技能実習制度の廃止理由を解説!新制度「育成就労」で何が変わるのか
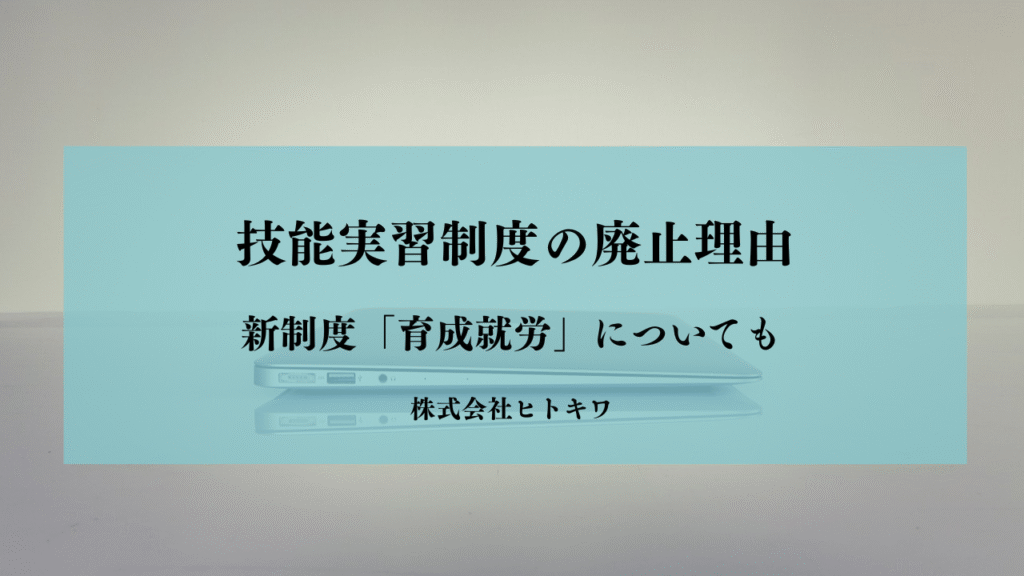
日本の外国人材受け入れ政策の大きな転換点として、長年にわたり国際貢献と人材育成を目的としてきた技能実習制度が廃止され、新制度である育成就労制度が導入される予定です。
この技能実習制度の廃止は、外国人労働者の育成と就労環境の問題解決を目指すものであり、企業や技能実習生本人だけでなく、日本全体に関わる重要なテーマです。
この記事では、技能実習制度が廃止される背景にある問題や、廃止の時期(いつから)、そして新制度である育成就労制度の具体的な概要を解説します。
特定技能制度との関係性や、企業が取るべき対応予定についても分かりやすく説明いたしますので、人材確保に関わる方はかならずご確認ください。
技能実習制度が「廃止」される背景と主な問題点

技能実習制度の廃止という大きな決定は、同制度が抱えてきた構造的な問題が背景にあります。
ここでは、技能実習制度の本来の目的と現実との乖離、そして廃止を求める声が高まった具体的な理由について深く掘り下げていきます。
① 技能実習制度の「廃止」が検討された主な理由
技能実習制度は、開発途上国への技能移転と人材育成を国際貢献の目的として創設された制度です。
しかし実際には、日本の外国人労働者を確保するための手段として利用されることが問題となり、国際社会からも「人道上の問題がある」と指摘されてきました。
本来の目的である国際貢献から逸脱し、安価な労働力確保を主眼とする運用実態が、制度の根本的な廃止の理由となりました。
この問題を解決し、外国人材の育成に真摯に向き合う新制度への移行が必要であるという結論に至ったのです。
② 制度が長年抱えていた問題点と批判の焦点
技能実習制度が長年抱えてきた問題点の最大の焦点は、技能実習生の人権侵害や劣悪な労働環境の存在です。
企業や監理団体による過度な支援費用の徴収、最低賃金以下の賃金での就労強制など、外国人であるがゆえの立場の弱さが悪用されるケースが問題視されてきました。
技能実習生が就労先を自由に選べない「転籍の制限」があるため、不当な扱いに直面しても企業を辞めることが困難でした。
こうした構造的な問題が、国際社会の非難を浴びる大きな原因となり、制度そのものを廃止し、能力向上を促す新制度へ切り替える必要性が高まりました。
③ 「廃止すべき」という議論が生まれた経緯
技能実習制度を廃止すべきという議論は、国内外の人権団体や労働団体から長期間にわたり強く主張されてきました。
彼らは、本制度が実質的には外国人の能力向上の場ではなく、日本の低賃金労働を支えるための人材確保手段になっていることを批判していました。
特に、実習生が企業との関係に不満があっても転籍できない点が「人権侵害」であると強く指摘され、制度の根本的な見直しが必要であると訴え続けられてきました。
こうした批判と、国際的な人権意識の高まりが、政府の検討会議で技能実習制度の廃止と、より就労を目的とした新制度への移行を決定づける要因となりました。
技能実習制度はいつから廃止され、新制度に移行するのか

技能実習制度が廃止され、新制度である育成就労制度へ移行することが決定しましたが、具体的な廃止の時期と新制度の施行予定は多くの関係者が最も注目している点です。
ここでは、最新の決定内容に基づき、今後のスケジュールと既存の技能実習生への影響を説明します。
① 技能実習制度「廃止」の決定時期と今後のスケジュール
技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設を含む法案は、2024年の通常国会で成立しました。
新制度の本格施行予定時期は、2027年4月1日が予定されています。(参照:日本経済新聞「外国人材の育成就労制度、27年4月から 政府閣議決定」)
これは、新制度を円滑に導入するための準備期間や、企業が移行するための支援を必要とするため、猶予期間が設けられていることを意味します。
この期間中に、新制度の詳細な要件や運用ルールが定められ、関連機関や企業への周知が進められます。
② 廃止後の移行期間と既存の実習生はどうなるか
技能実習制度の廃止後、すでに日本で技能実習生として就労している外国人には、新制度への円滑な移行措置が講じられる予定です。
新制度が施行された後も、既存の技能実習生は残りの実習期間を技能実習制度のもとで継続することが可能です。
技能実習制度の目的を達成し、技能水準が一定能力に達した外国人は、新制度の育成就労制度や特定技能制度へ移行することが可能となります。
この移行については、実習生の技能習熟度や、新制度の要件を満たしているかを個別に判断するための支援体制が必要とされ、関係機関が計画を立てています。
新制度「育成就労制度」の具体的な概要
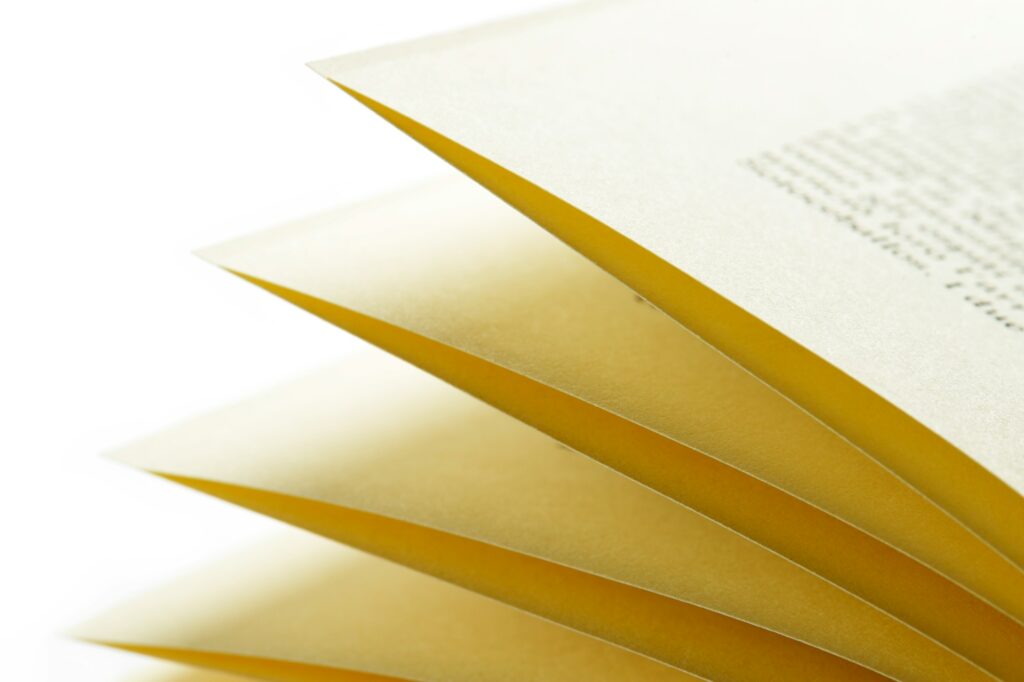
技能実習制度の廃止を受けて創設される「育成就労制度」は、これまでの問題点を根本から解決し、外国人労働者の育成と安定的な就労を真の目的としています。
ここでは、この新制度の核心となる部分と、従来の制度との違いを詳しく見ていきます。
① 「育成就労制度」の目的と技能実習制度との大きな変更点
育成就労制度の最大の目的は、外国人に技能を習得させるだけでなく、就労を通じて能力を向上させ、人材として育成することにあります。
技能実習制度における監理団体は廃止され、今後は「育成支援機関」として再編される予定です。
技能実習制度との大きな変更点は、外国人労働者の転籍が原則として可能になる点であり、能力に応じて企業を選べる自由度が向上します。
また、技能と日本語能力の向上を必須とする要件が課せられ、育成を目的とする制度であることを明確にしています。
この新制度では、外国人が長期的に日本で就労し、日本の人材確保に貢献できる仕組みを築くことが目指されています。
② 新制度における外国人労働者の転職・移籍はどうなる
新制度である育成就労制度では、外国人労働者が一定期間の就労を経た後、転籍することが可能になる点が画期的な変更点です。
具体的な要件としては、同一の企業で1年から2年程度の就労期間が必要とされ、その間に技能や日本語能力の試験に合格することが転籍の条件となる予定です。
この転籍の自由は、外国人労働者が不当な待遇を受けた場合に企業を変更できるようにすることで、技能実習制度における人権問題の解決に繋がります。
企業側は、転籍を防ぐために外国人への育成や支援をより真剣に行う必要があり、人材の確保に向けた競争が生まれることが期待されています。
③ 育成就労制度が解決を目指す問題点
育成就労制度が解決を目指す最大の問題点は、技能実習制度が「建前と実態が乖離している」と批判されてきた点です。
外国人の育成という目的を果たしながら、同時に日本の人材確保にも貢献する仕組みを構築することで、制度の透明性と正当性を高めます。
また、技能実習生に転籍の自由を与えることで、企業間の健全な競争を促し、外国人労働者の能力や処遇が向上することが目的です。
新制度では、技能と日本語の試験を課すことで、外国人が能力を証明し、より上位の在留資格である特定技能へと移行しやすい道筋を明確にします。
新制度と特定技能制度との関係
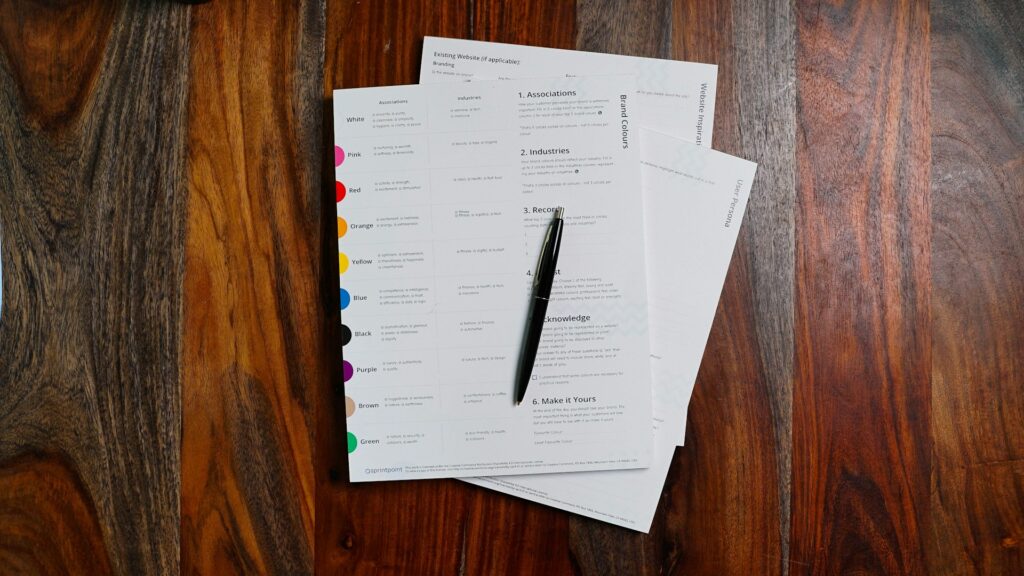
育成就労制度は、特定技能制度と並行して運用される予定であり、外国人が日本でキャリアを築くための道筋を明確にする制度です。
ここでは、新制度が特定技能制度とどのような関係を持ち、外国人労働者の移行がどのように変化するのかを具体的に説明します。
① 特定技能1号・2号への移行条件と新制度での位置づけ
育成就労制度は、特定技能1号・2号の在留資格へ移行するための準備段階として位置づけられています。
新制度の対象職種は、特定技能制度の12分野に準拠することが明確にされており、移行時の整合性が大幅に向上します。
特定技能1号への移行は、育成就労制度で育成された外国人が、一定能力の技能と日本語能力を試験で証明することで可能になります。
技能実習制度では複雑だった特定技能制度への移行プロセスが、新制度の導入により簡素化され、外国人の就労継続の目的を達成しやすくなります。
② 育成就労制度の導入で特定技能制度はどう変わるのか
育成就労制度の導入により、特定技能制度は、外国人が長期的に日本で就労し、永住権の取得も視野に入れるための上位資格としての役割が明確になります。
技能実習制度では「人材育成」という目的が曖昧であったため、特定技能制度への移行が実習生の就労継続の目的となってしまう問題がありました。
新制度は、育成を目的としつつも、就労を前提としているため、特定技能制度への移行がより自然で論理的なキャリアパスとなります。
育成就労制度と特定技能制度は、それぞれが人材の育成と即戦力としての確保という明確な役割を持ち、日本の外国人労働者確保体制を支える二本の柱となります。
よくある質問(FAQ)
技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行に関して、企業や外国人労働者の皆様から寄せられることが多い質問とその回答をまとめました。
新制度について疑問がある場合は、かならずご確認ください。
育成就労制度が導入された後も技能実習生は日本に来られますか
育成就労制度が施行された後は、技能実習制度の枠組みでの新規受け入れは廃止されます。
しかし、新制度である育成就労制度のもとで、技能や能力の育成を目的とした外国人の受け入れは継続されます。
外国人労働者の採用を希望する企業は、育成就労制度の要件を満たした機関を通じて人材確保を行うことが必要になります。
育成就労制度への移行は誰でもできるのでしょうか
すでに技能実習生として就労している外国人には移行措置が設けられますが、誰でも無条件で移行できるわけではありません。
新制度へ移行するためには、日本語能力や技能水準が一定の要件を満たしている必要があり、試験に合格することが条件となります。
企業は、移行を希望する技能実習生の支援と育成に積極的に取り組むことが求められます。
技能実習生を雇用している企業は何をすべきでしょうか
技能実習制度の廃止後も、既存の実習生の育成と支援を継続することが必要です。
新制度の育成就労制度へ円滑に移行できるよう、日本語教育や技能向上のための計画を立て、実習生の能力向上の支援を強化してください。
また、新制度では転籍が可能となるため、人材確保のためには処遇の改善や働きやすい環境作りが重要となります。
新制度における「転籍」の自由度はどれくらいですか
育成就労制度では、原則として転籍が可能となりますが、無制限な自由ではありません。
新制度では、同一企業での1年から2年程度の就労期間を経た後、一定の要件(日本語・技能の試験合格など)を満たすことが転籍の条件となる予定です。
これは、育成を目的とする制度の趣旨を守るため、安易な転籍を防ぐ目的があります。
特定技能と育成就労制度の違いは何ですか
特定技能制度は、特定の分野で即戦力となる人材確保を目的とした在留資格です。
一方、育成就労制度は、外国人に技能と日本語を習得させ、人材として育成することを主な目的としています。
育成就労制度は、特定技能1号へ移行するためのキャリアのスタート地点として位置づけられ、二つの制度が連携して外国人労働者を確保する役割を担います。
まとめ
技能実習制度の廃止と育成就労制度の導入は、日本の外国人労働者受け入れの歴史における重要な転換点です。
新制度は、技能実習制度が長年抱えてきた人権問題や目的と実態の乖離を解決し、真に育成と就労を目的とした制度へと移行を目指します。
廃止の時期は2027年4月1日が予定されており、企業はこの移行期間中に新制度の要件と特定技能制度との関係性を理解し、外国人材確保の計画を再検討することが必要です。
育成就労制度の導入は、外国人労働者に転籍の自由を与え、日本語能力の向上を必須とするため、企業にはより質の高い育成支援が求められます。
この新制度が、外国人労働者と企業の双方にとって公正で持続可能な人材確保の基盤となることが期待されています。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。