技能実習制度の基本から新制度までわかりやすく解説
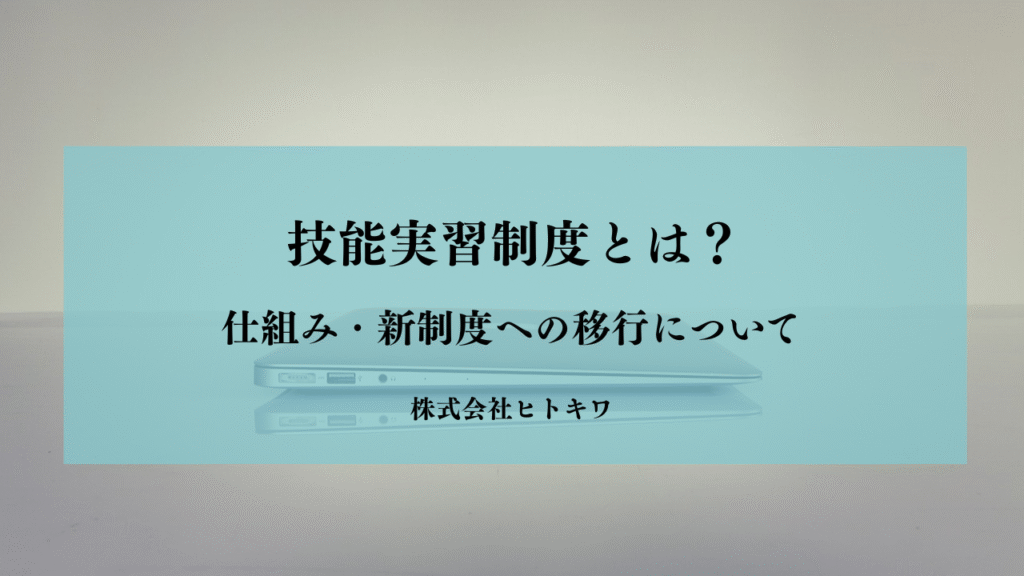
技能実習制度は、発展途上国などのかたがたに日本のすぐれた技能や知識を移転し、その国の経済発展を担う人づくりを支援するという、国際貢献を目的として1993年から始まった大切な制度です。
しかしながら、近年、この制度が労働力の確保を目的とした手段になってしまっているという指摘や、実習生をめぐるさまざまな問題点がたびたび報道されるようになり、大きな注目を集めることとなりました。
現在、政府の話し合いによって、この技能実習制度は廃止され、新しい制度である育成就労制度に移行することが決定していますので、受け入れ企業の担当者様はもちろん、関心をお持ちのすべてのかたにわかりやすく解説します。
新旧の制度の違いや、いつから制度が変わるのかというスケジュール感についても、最新の情報をもとにお伝えしていきます。
技能実習制度とは?目的と基本的な仕組み

この技能実習制度は、国際貢献という非常にすばらしい目的のもとに作られた制度ですが、具体的にどのような仕組みで技能実習生が日本で学んでいるのかを掘り下げていきます。
実習生を受け入れるためにどのような要件があるのか、どのような職種が対象なのか、基本的なルールをしっかりと理解することで、この外国人技能実習制度の全容がみえてきます。
① 技能実習制度の概要
技能実習制度の概要を以下の表にまとめます。
この制度は、日本の企業が外国人のかたを受け入れ、OJT(働きながら)を通じて特定の技能を習得していただくための在留資格です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 国際貢献(発展途上国への技能・知識移転による人づくり支援) |
| 在留資格 | 技能実習(OJTを通じて技能を習得) |
| 基本的な考えかた | 帰国後、母国の産業・経済発展に貢献すること |
| 実習期間 | 原則として最長で5年 |
| 期間の段階 | 1年目:技能実習1号 / 2~3年目:2号 / 4~5年目:3号 |
| 企業側の責務 | 労働基準法などを守った適切な労働条件の提供、計画に沿った指導員の教育 |
② 技能実習制度の運用領域
技能実習制度の運用領域は、主務省庁である法務省、厚生労働省などが定めている運用要領によって細かく規定されており、法令順守が厳しく求められています。
運用要領には、実習計画の認定基準や、受け入れ企業が守るべきルールのすべてが明確に示されていますので、実施者の企業様はかならず内容を確認しなければなりません。
また、技能実習生がスムーズに実習を行うことができるよう、監理団体と呼ばれる非営利の機関が実習実施者の企業をサポートし、計画通りに実習が進んでいるかをチェックする役割を担っています。
運用要領を無視した不適切な実習は、企業や監理団体に対して指導や改善命令、場合によっては許可の取り消しといった厳しい処分が下されることになりますので注意が必要です。
③ 制度の目的と対象となる職種
技能実習制度の一番の目的は、あくまでも国際貢献であり、人手不足を補うための労働力確保ではないという点を、受け入れ企業は深く理解しておく必要があります。
実習生の対象となる職種は、農作業、漁業、製造業、建設関係、食品加工、介護など、さまざまに分かれており、現在は87の職種と165の作業が認められています。(参照:厚生労働省「外国人技能実習制度について」)
どの職種や作業で実習を受け入れることができるのかについては、定められた要件を満たし、その分野での実習が適切であると認められた場合のみ、実習計画の認定を受けることが必要です。
実習生が日本での実習を通じて確かな技能を身につけ、母国に帰ってからも活躍できるような、質の高い指導を提供することが制度の真の目的に沿うことになります。
④ 技能実習生を受け入れるための要件
技能実習生を受け入れることができる企業、つまり実習実施者には、実習を適切に実施するための厳しい要件が定められており、すべての基準をクリアする必要があります。
主な要件は以下の通りです。
| 要件項目 | 概要 |
|---|---|
| 指導員の配置 | 実習生を指導するための専門知識と経験を持った指導員を必ず配置すること。 |
| 設備・施設の整備 | 実習内容に必要な設備や施設を整えること。 |
| 生活指導員の選任 | 実習生の生活面でのサポートを行う生活指導員を選任すること。 |
| 宿泊施設の確保 | 実習生が安心して生活を送るための宿泊施設を確保すること。 |
| 法令遵守・人権保護 | 実習生への差別的な取り扱いや人権侵害がないよう、法令を遵守し、実習生を大切にする姿勢を持つこと。 |
⑤ 監理団体と届出制の重要性
監理団体は、実習実施者である企業が適正に技能実習を実施しているかを監理する非営利の団体であり、技能実習制度を支える大切な機関です。
監理団体は、実習生の入国から帰国までを一貫してサポートし、企業と実習生との間のトラブルを未然に防ぎ、実習生が安心して技能習得に専念できる環境を整える役割があります。
この団体は、外国人技能実習制度の健全な運用を保つために、許可を受けた機関として年間の実習計画や実施状況を届け出る必要があり、その監理が制度の信頼性につながります。
実習実施者の企業が監理団体を通さずに実習生を受け入れることは一部例外を除いてできませんので、信頼できる団体との連携が必要となります。
技能実習制度が抱える問題
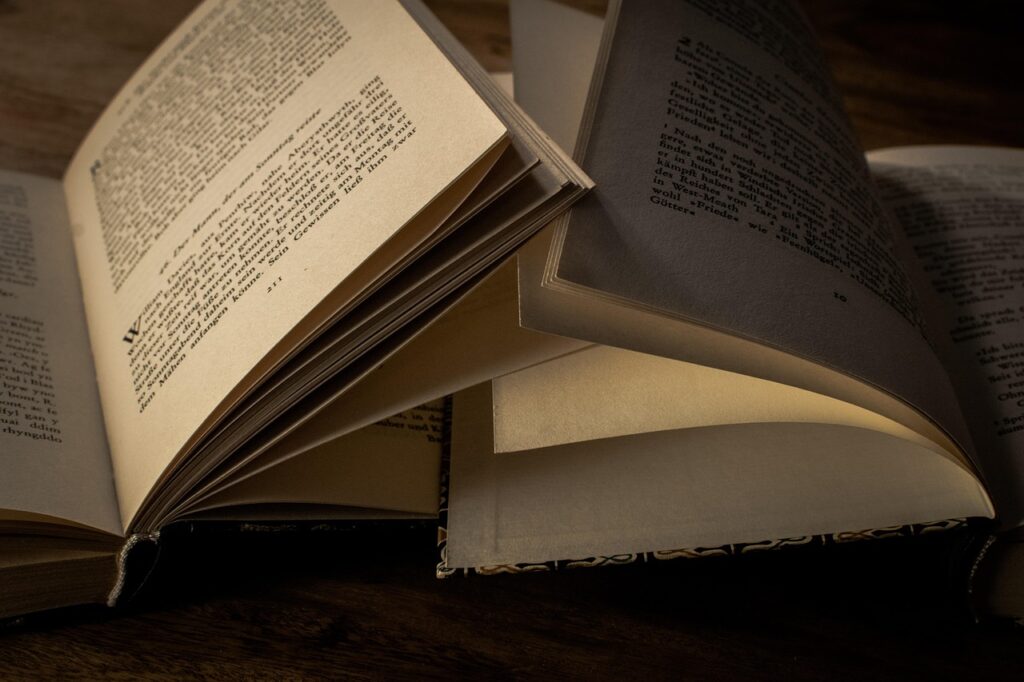
国際貢献という崇高な目的を持つ技能実習制度でしたが、その運用の中で、本来の目的にそぐわないさまざまな問題点が顕在化してしまった経緯があります。
特に、実習生のかたがたの権利や労働環境に関わる問題は、制度の見直しを議論する上で非常に重要な焦点となりましたので、主な問題点を詳しくご説明します。
① 賃金や労働環境に関する問題
技能実習生のかたがたの賃金が、日本人の労働者と比較して不当に低い水準に設定されているのではないかという問題が、以前からたびたび指摘されてきました。
最低賃金法は適用されますが、実習実施者によっては、そこぎりぎりの賃金で実習生を雇用し、さらに寮費などを控除して実質的な手取り額が非常に少ないという事例も見受けられました。
また、長時間労働や、危険な作業を実習名目で行わせるなど、実習生の安全と健康が守られていない不適切な労働環境が問題となり、制度の信頼性を大きく揺るがすことになりました。
実習生も1人の労働者として、日本で働くかたがたと同じように、適切な賃金や労働環境のもとで実習を行うことができるということが、人権を守る上で重要です。
② 転職や職種の変更が難しい点
これまでの技能実習制度においては、原則として実習生は実習実施者の企業からほかの企業へ転職することが極めて難しく、事実上不可能な状況となっていました。
この転職の制限があることで、実習生は不当な労働条件やハラスメントを受けた場合でも、企業を変えることができず、泣き寝入りせざるを得ないという構造的な問題を生じさせていました。
また、実習の途中で実習生が体調を崩してしまった場合や、実習を継続することが困難になった場合でも、職種の変更や実習先の変更が柔軟に認められないという課題もありました。
実習生が安心して実習に専念し、万が一のときに自分の意思を尊重されるためにも、転職や職種の変更を柔軟に認める仕組みが必要であると議論されていました。
③ 目的と実態のズレ
技能実習制度の本来の目的が国際貢献であるにもかかわらず、多くの日本企業において、実態としては人手不足を補うための労働力確保の手段として利用されてきたという現実があります。
特に、若くて健康な外国人労働力を安定的に確保したいという企業の思惑と、制度の目的とが大きくずれていたことが、さまざまな問題を引き起こす根本的な原因となっていました。
この制度が労働力確保の手段として使われることで、実習生を低賃金で酷使するような悪質な企業が増加し、制度全体に対する社会的な批判が強まる結果となりました。
国際社会からも、日本の制度が実習生の人権を侵害しているのではないかという厳しい目が向けられたため、制度そのものを根本から見直す必要性が高まったのです。
④ 悪質な実習実施者への処分強化
技能実習制度の問題の根底には、一部の実習実施者である企業による不適切な実施があり、これに対する処分の強化が長年の課題となっていました。
実習生の人権を無視した労働環境の提供や、最低賃金を下回る賃金での作業の強要といった問題行為が発覚した場合、監理団体や関係機関による厳しい調査が行われます。
外国人技能実習制度の信用を揺るがす企業に対しては、技能実習の許可が取り消されたり、新たな実習生の受け入れが停止されたりといった重い処分が実施されることになります。
企業が法令を遵守し、実習生を単なる労働力ではなく、技能を学ぶ大切な人材として育成するという意識を持つことが、問題を解決する必要な一歩となります。
技能実習制度はいつ廃止される?
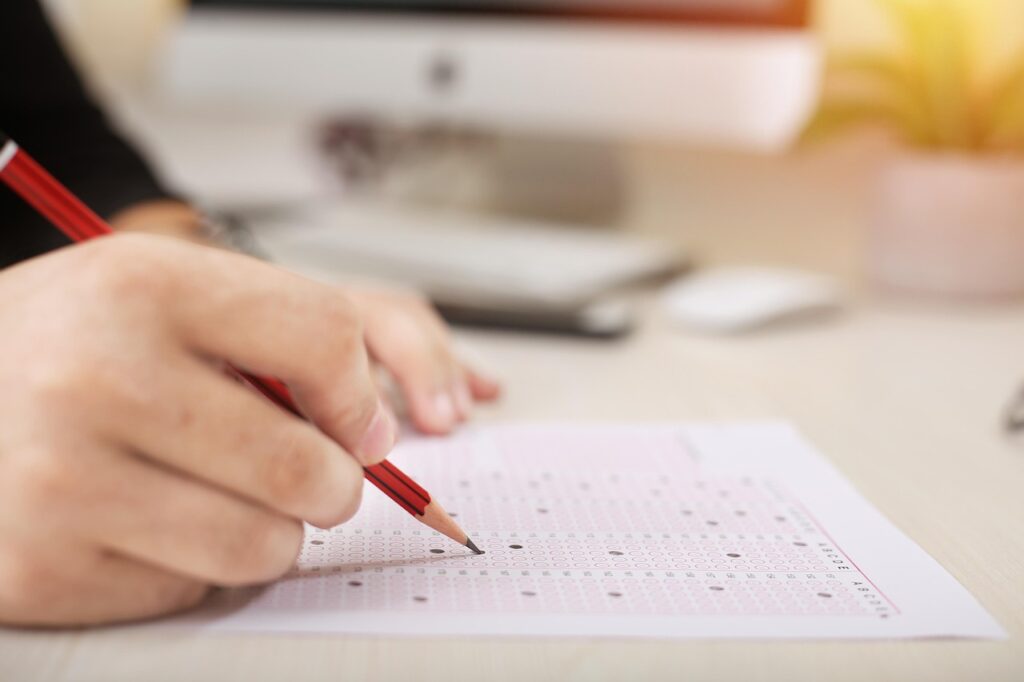
数多くの問題点と、国際社会からの批判を受け、政府の専門家会議で技能実習制度のありかたが徹底的に議論され、その結果、現在の制度は廃止されることが決定しました。
それでは、この重要な決定がいつから実施されるのか、そしてどのような議論を経て新制度へと生まれ変わることになったのかを、詳しく見ていきましょう。
① 廃止の決定と今後のスケジュール
技能実習制度を廃止し、新たな制度へ移行するという決定は、2023年に開かれた政府の有識者会議の最終報告書において正式に提言され、政府もそれを了承しました。
ただし、制度の廃止は即座に行われるわけではなく、新しい「育成就労制度」を導入するための法整備や関係規定の整備に時間を要するため、段階的に進められる予定です。
新制度の具体的な施行日は、9月26日に行われた政府の閣議によって2027年4月1日と決定されましたので、同じ時期に技能実習制度の廃止も進められることが予想されます。(参照:日本経済新聞「外国人材の育成就労制度、27年4月から 政府閣議決定」)
施行日までは現行の技能実習制度運用要領に基づき、適正な実習の実施と実習生の保護が引き続き求められることになりますので、準備を進める必要があります。
② 制度見直しで議論された重要論点
技能実習制度の見直しを議論するにあたって、最も重要視された論点は、「人権の保護」と「労働力の確保」という2つの側面をどのように両立させるかという点でした。
これまでの制度で禁止されていた、実習生の転職の自由をどこまで認めるべきかという点や、不当な人権侵害を防止するための監理・監督体制の強化が重要なテーマとなりました。
また、国際貢献という名目ではなく、労働者の育成と日本での就労を目的とするという、制度のありかたそのものを根本から見直すという議論も深く行われることになりました。
その結果、実習生が日本で技能を習得したあと、より専門性の高い特定技能の在留資格へスムーズに移行できるような仕組みを作ることが、新たな制度の柱として検討されたのです。
③ 新制度「育成就労制度」への移行
技能実習制度の廃止にともない、そのあとを引き継ぐ新しい在留資格として「育成就労制度」が創設され、今後この制度へ段階的に移行していくことになります。
育成就労制度は、従来の技能実習制度が抱えていた人権問題や目的のあいまいさを解消し、実習生がキャリアアップできるような、より明確な道筋を示すことを目指しています。
これまでの制度で問題となっていた、実習生の実習実施者変更、つまり転職の制限についても、一定の条件のもとで柔軟に認められるような仕組みが導入される予定です。
新しい制度に移行することで、外国人技能実習生として日本に来るかたがたのモチベーションを高め、受け入れ企業の企業活動においてもより透明性の高い運用が期待されます。
④ 「特定技能」制度への接続と違い
技能実習制度と新制度の背景には、外国人材の長期的な就労を目的とした「特定技能」という在留資格との接続をいかにスムーズにするかという大きな課題がありました。
特定技能は、技能実習を修了した外国人が、さらに高い技能をもって日本で就労することを許可する制度であり、実習で培った技能の延長線上に位置づけられています。
新しい育成就労制度は、この特定技能への移行を前提とした制度設計となっており、実習生が将来的に日本で働くことを視野に入れたキャリア形成を支援する目的があります。
実習生の人数も年間の実施数も関係してくる特定技能へのスムーズな移行は、日本の産業界全体の労働力確保に必要不可欠な要素となっています。
新制度「育成就労制度」とは?

技能実習制度が廃止され、あらたに導入が予定されている「育成就労制度」は、今後の日本の外国人労働者のありかたを大きく変えることになる、非常に重要な制度です。
この新制度がどのような特徴を持ち、従来の制度と比べてどのような点が大きく変わるのかを理解しておくことは、企業のかたがたにとって必要不可欠なことになります。
① 育成就労制度の概要
育成就労制度は、外国人のかたがたが日本で働きながら技能を習得し、その知識や経験を生かしてキャリアアップすることを正面から支援するという、新しい在留資格です。
この制度は、技能実習制度の反省点を踏まえ、実習生の人権を守りつつ、将来的に特定技能の在留資格へスムーズに移行できるような、就労を目的とした枠組みとして設計されました。
実習期間中に一定の要件を満たすことで、実習実施者の企業を変えること、つまり転職を認めることで、実習生が不当な環境から逃れることができるように配慮されています。
育成就労制度は、外国人材の安定的な確保と、その育成を国の重要な政策として位置づけるという、これまでの制度とは根本的に異なる考えかたに基づいています。
② 育成就労制度の主な変更点と目的
育成就労制度の最も大きな変更点は、実習生が実習実施者の企業を移籍すること、いわゆる転職が緩和されることであり、これは実習生のかたがたの自由度を高める重要な一歩です。
また、この制度の目的は、技能実習制度の国際貢献というあいまいな名目から、外国人材の「育成」と「確保」へと明確に変更され、実態に即した内容となりました。
外国人材の育成をより確実にするために、実習実施者への監理監督を強化し、実習生の日本語能力の向上を促すための支援なども手厚く行うことが予定されています。
この新しい制度の導入は、日本の産業界における外国人材の受け入れをよりオープンで透明性の高いものにし、持続可能な外国人労働力確保の実現を目指すものです。
③ 新制度への移行はいつから始まるのか
新制度である育成就労制度への移行は、2027年4月1日に始まります。
これに伴い、現行の技能実習制度は廃止されます。
移行期間中は、現行の技能実習制度と新しい育成就労制度が並行して存在する期間がある可能性もありますので、法務省などの公的な機関からの情報を注意深く確認する必要があります。
受け入れを検討している企業は、制度の変更にともなって実習計画や監理体制を新しい基準に適合させるための準備を、早めに始めることが大切になります。
新しい制度がいつから始まるのかという情報をしっかりと把握し、スムーズな移行を実施することで、外国人材を安定的に受け入れるための体制を整えることができるでしょう。
④ 育成期間と特定技能への移行パス
育成就労制度では、実習生の日本での育成期間が明確に定義され、この期間を経て特定技能の在留資格へのスムーズな移行パスが設けられることになります。
実習生は、所定の育成期間中に技能と日本語能力を必要な水準まで高めることが求められ、特定技能への許可を得るための試験などに挑戦することになる予定です。
この移行パスが明確になることで、実習生は日本でのキャリアプランを描きやすくなり、高いモチベーションをもって作業や実習に臨むことができるようになります。
実習実施者の企業にとっても、実習生を長期的に特定技能外国人として雇用できる見通しが立つため、人材育成への投資を行いやすくなるというメリットが生まれるでしょう。
よくある質問(FAQ)
技能実習制度や新しい育成就労制度については、制度の複雑さからさまざまな疑問をお持ちになるかたが多くいらっしゃいますので、こちらでよくあるご質問にお答えします。
特に、お金のことや、新旧の制度の違いなど、多くのかたが気になるポイントを厳選しましたので、ぜひ参考にしてください。
① 技能実習制度の補助金はどんなものがありますか?
技能実習制度について、国による直接的な補助金は基本的にはありません。
ただし、自治体によっては地域独自の助成金制度を設けている場合がありますので、お住まいの地域や実習実施者の自治体ホームページを確認するのがよろしいでしょう。
また、実習生が特定技能へ移行する際の日本語学習支援など、間接的なサポート制度が利用できることもありますので、公的機関の情報を調べてください。
② 新制度「育成就労制度」との違いは?
育成就労制度は、技能実習制度の目的に加え「外国人材の育成と確保」を明確にした新制度です。
最大の変更点は、一定の条件のもとで実習生が転職できるようになったことで、人権保護と自由度が大幅に強化されました。
新制度では日本語能力の向上が促され、特定技能へのスムーズな移行が期待できる点も大きな違いです。
③ 技能実習の対象となる職種を知りたい
技能実習の対象職種は、製造業、建設関係、農作業、介護など、87職種と165作業に分かれており、非常に多岐にわたります。
実習実施者の企業は、運用要領に含まれている職種かかならず事前に確認し、適切な実習計画を立てる必要があります。
これは、実習生が母国に帰国後も技能を活かせるようにという国際貢献の目的に沿って選定されているのです。
④ 制度の運用要領はどこで確認できますか
制度の運用要領は、法務省と厚生労働省の共同所管で、出入国在留資格管理庁や外国人技能実習機構の公式ホームページで最新版を無料で確認することが可能です。
この運用要領には、実習実施者の要件や、実習計画の認定基準、人権保護のルールなど、実務に必要な情報が細かく定められています。
新制度への移行後も、公的機関からの情報をこまめにチェックするように心がけてください。
⑤ 実習生とのコミュニケーション(英語など)はどうする
技能実習生とのコミュニケーションは、原則として日本語で実施することが基本です。
実習生は入国前に日本語の基礎を学んでいますが、企業側も日常の作業指示や生活指導には、わかりやすい日本語を使う工夫が必要です。
監理団体が通訳を配置したり、翻訳アプリを活用したりするなど、スムーズなコミュニケーションをサポートする体制を整えることも大切です。
まとめ
本日は、日本における外国人材受け入れの柱であった技能実習制度の基本的な仕組みから、制度が抱える問題点、そして今後の廃止と新制度への移行について詳しくご説明しました。
技能実習制度は、国際貢献という大切な役割を果たしてきましたが、実態とのズレや人権侵害などの問題から、廃止という大きな見直しが決定したというのが現状です。
今後は、外国人技能実習制度の廃止にともない、外国人材の育成と確保を目的とした、より透明性の高い「育成就労制度」へと、2027年4月1日から移行していくことになりますので、その動向に注目する必要があります。
新しい制度は、実習生が転職できる自由を認めるなど、実習生の人権保護を大幅に強化した内容となっており、企業にとってもより安心して外国人材を受け入れられる仕組みを目指しています。
受け入れ企業のかたがたは、新制度の施行日である2027年4月1日を目標に、制度運用要領などを確認し、適正な受け入れ体制を整えるための準備を進めてください。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。