外国人雇用トラブルを未然に防ぐ!事例・原因・対策法を徹底解説
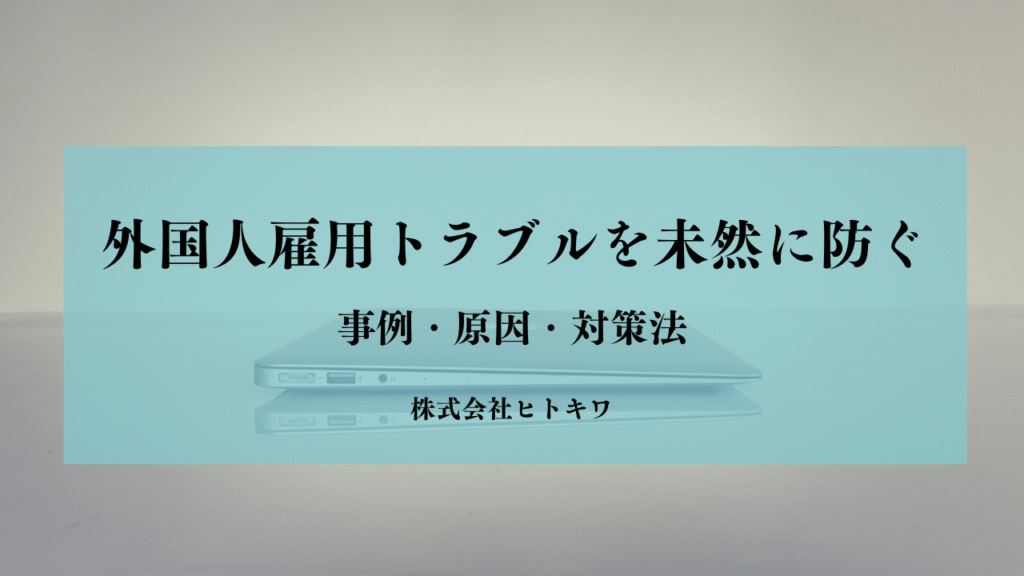
外国人労働者の雇用が広がるなか、言葉や文化の違いから思わぬトラブルに直面するのではないかと不安を抱えている企業様も多いのではないでしょうか。
本記事では、外国人雇用で実際に起こりやすいトラブルの具体的な事例とその根本的な原因について深く掘り下げていきます。
またトラブルを未然に防ぐための有効な対策法や、万が一問題が発生したときの対処法まで詳しく解説いたしますので、貴社が外国人労働者と日本人社員が共に安心して働ける職場環境を築くための手助けとなることでしょう。
外国人雇用でよくあるトラブルの具体例

外国人労働者を雇用する際、文化や習慣の違いから思わぬトラブルに発展することがあります。
ここでは特に日本企業でよく見られる具体的なトラブル事例をいくつかご紹介いたしますので、自社の状況と照らし合わせてみてください。
①言葉や文化の壁から生じるトラブル
コミュニケーションは、職場を円滑に運営するために欠かせない要素です。
しかし日本語能力がまだ不十分な外国人労働者と意思疎通がうまくいかず、業務の指示が正確に伝わらなかったり、意図しない誤解が生じたりすることがよくあります。
また日本の商習慣である「報連相(報告・連絡・相談)」の文化を理解しておらず、問題が起こっても報告が遅れてしまうこともトラブルの一因となります。
お互いの文化やコミュニケーションに対する考え方の違いを理解できなければ、ストレスや不信感につながってしまうこともあるのです。
②労働条件や契約内容に関するトラブル
労働条件や契約内容の認識のズレもよくあるトラブルの一つです。
特に日本の労働基準法や雇用慣行は複雑なため、外国人労働者が給与計算の方法や時間外労働、有給休暇のルールなどを十分に理解できない場合があります。
その結果、賃金の未払いや不当な労働を主張するなど、後から大きな問題に発展することがあります。
採用時に交わした契約書の内容を外国人労働者の母国語でしっかりと説明し、双方が納得するまで確認し合うことが非常に大切になります。
③在留資格やビザに関するトラブル
在留資格やビザに関する問題は、企業にとって非常に大きなリスクとなります。
外国人労働者が所持する在留資格の活動内容と、実際の業務内容が異なっていたり、在留期間が過ぎていたにもかかわらず気づかずに働かせてしまったりする事例があります。
これらの問題は雇用する企業側も法律違反となり、罰則の対象となるだけでなく、外国人労働者自身も不法滞在となり日本での生活を続けられなくなるなど、双方にとって深刻なトラブルになってしまうのです。
外国人労働者とのトラブルになったニュース事例

実際にニュースなどで報じられている外国人労働者とのトラブル事例を知ることで、自社で起こりうるリスクを事前に把握できます。ここでは代表的な事例を紹介します。
①人権侵害やハラスメントの事例
韓国で起きた外国人労働者に対する集団いじめは、フォークリフトに縛り付けられた映像がニュースとして世界中に拡散され、大きな社会問題となりました。
これは日本でも起こりうる事例であり、外国人労働者が日本語が通じないことを理由に暴言や暴行を受けるといった人権侵害やハラスメントの事例も報道されています。
人種や国籍を理由にした差別的な行為は決して許されるものではなく、企業は厳格なハラスメント対策を講じることが必要です。
(出典:TBS NEWS DIG )
②賃金不払いや違法な長時間労働の事例
外国人技能実習生に対して最低賃金を下回る賃金しか支払われなかったり、長時間労働を強いられたりするケースが、厚生労働省の調査やニュースで報告されています。
違法な賃金未払いは、企業が罰金や懲役といった罰則を受けるだけでなく、社会的な信用を失うことにもつながります。
外国人労働者を雇用する際は、労働基準法を遵守し、賃金や労働時間を適正に管理することが非常に大切です。
(出典:厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況」)
③不法就労や在留資格の不正取得の事例
雇用主が、在留期間が切れた外国人労働者を不法に雇用したとして逮捕されたり、就労資格のない外国人を企業に派遣していた人材会社が摘発されたりする事例も発生しています。
これらは雇用する企業側が不法就労助長罪に問われ、重い罰則を受けることになります。
外国人労働者を雇用する際には、在留カードを厳格に確認し、就労が認められる在留資格であるか、期限が切れていないかを徹底的にチェックすることが不可欠です。
(出典:全国外国人雇用協会)
外国人雇用でトラブルが起こる原因

外国人雇用で発生するトラブルは決して珍しいことではありませんが、その多くは事前の準備や日々のコミュニケーション不足が原因となっています。
ここでは外国人労働者とのトラブルを未然に防ぎ、解決するために知っておくべき根本的な原因について解説します。
①採用前の情報共有が不十分
外国人労働者の採用を急ぐあまり、入社前に十分な情報共有ができていないケースがよく見られます。
業務内容や労働時間、給与体系、職場のルールや雰囲気を曖昧にしたまま採用すると、入社後に「話が違う」と感じる原因になります。
外国人労働者が抱く期待と実際の仕事内容に大きなギャップが生まれてしまい、早期離職や深刻なトラブルに発展してしまうのです。
丁寧な説明と正確な情報提供が、トラブルを防ぐ第一歩となります。
②職場でのコミュニケーション不足
言葉の壁があると、どうしても日常的なコミュニケーションが減ってしまいがちですが、これによりお互いの理解が深まらず、小さな誤解が解消されないまま放置されてしまいます。
特に仕事の進捗状況や困っていることについて話し合う機会がなければ、問題が大きくなるまで気づくことができません。
外国人労働者は孤立感を感じやすくなり、職場での不満がたまってしまい、やがて雇用問題に発展する可能性がありますので、日々の積極的な声かけや交流がとても大切です。
③文化的背景や習慣の違いへの理解がない
日本人が当たり前だと思っている習慣や文化が、外国人労働者にとっては全く異なる場合があります。
たとえば、時間に厳格であることや、上司への敬意の示し方、意見を直接言わないといった日本独自の文化は、彼らにとって戸惑いの原因となることがあるのです。
このような文化的背景の違いを企業側が理解し、外国人労働者に対しても日本の習慣を丁寧に説明しなければ、すれ違いが生じてしまいます。
お互いの文化を尊重し理解しようとすることが、トラブルの発生を抑制します。
外国人雇用トラブルを未然に防ぐための対策方法

外国人雇用で発生しうるトラブルの多くは、事前の対策で回避することができます。
適切な準備と対応を講じることで、企業はリスクを減らし、外国人労働者も安心して働ける環境を整えられます。
ここでは、すぐに取り組める具体的な対策を紹介します。
採用前の段階で準備すべきこと
採用の前に、外国人労働者が業務内容や労働条件を正確に理解できるような工夫をすることが重要です。
例えば、募集要項や雇用契約書は、日本語だけでなく、外国人労働者の母国語で作成することがおすすめです。
面接時には、第三者の通訳を挟んで話し、お互いの疑問点を丁寧に解消しておくことも有効な対策となります。
また、外国人労働者が持つ在留カードをかならず確認し、就労可能な在留資格であるかをしっかりと確認することも、トラブル回避には必須です。
日本語の能力を過信しない
日本語能力試験で高い点数を持っている外国人労働者でも、専門的な業務内容や複雑な日本の職場文化を完全に理解しているとは限りません。
特に日本語でスムーズな会話ができる場合でも、細かいニュアンスや行間を読み取ることが難しいことがあります。
そのため企業側は、専門用語を避けたり、視覚的な資料やジェスチャーを交えたりするなど、分かりやすいコミュニケーションを心がけることが大切です。
相手の理解度を確認しながら、丁寧に指導することで、業務上のミスや誤解を減らせます。
トラブル発生時の相談窓口を明確化する
外国人労働者が困ったときに、すぐに相談できる窓口を社内に設けておくことも非常に重要です。
相談窓口として指定された担当者は、外国人労働者が母国語で相談できるような準備を整えておくことが望ましいです。
これにより、言葉の壁を気にすることなく、気軽に悩みを打ち明けられる環境が生まれます。
こうした信頼関係を築くことで、小さな不満が大きなトラブルに発展する前に、早めに問題を解決できるようになるでしょう。
外国人トラブル発生時の具体的な対処法

万が一、雇用トラブルが発生してしまった場合でも、焦らず冷静に対応することが重要です。
適切な対応をすることで、問題の悪化を防ぎ、外国人労働者との信頼関係を維持することができます。
ここでは、状況別の具体的な対応策を解説します。
適切な相談先を選ぶ
外国人労働者とのトラブルが個人で解決できない場合、外部の専門機関に相談することは非常に有効な手段となります。
例えば、給与の未払いなど労働基準法に関する問題であれば、最寄りの労働基準監督署に相談することができます。
また、労働者と使用者間の紛争であれば労働局が解決をサポートしてくれますし、専門的な法律問題については外国人労働者の雇用に詳しい弁護士に相談することがもっとも確実な解決策となるでしょう。
適切な相談先に連絡することで、問題をスムーズに解決に導くことが可能です。
労働基準法を遵守してることを明確にする
外国人労働者であっても、日本の労働基準法が適用されます。
そのため日本人労働者と同じように労働時間や最低賃金、割増賃金、有給休暇の付与などを法律に基づいて管理し遵守することが不可欠です。
外国人労働者との雇用契約書を作成する際は、日本の労働基準法に準拠していることを明確にし、外国人労働者が内容を十分に理解できるように母国語での説明や通訳を準備することが重要になります。
法律を遵守することで、給与未払いや不当な解雇などのトラブルを防げます。
日本語と母国語両方で対応する
トラブルが発生した際には、外国人労働者が十分に理解できるよう日本語と母国語の両方で対応することが大切です。
日本語が苦手な外国人労働者にとっては、日本人の説明だけでは内容を正確に把握できず、誤解がさらに深まってしまう可能性があります。
そのため、通訳を交えたり、書面でのやり取りであれば母国語に翻訳したりするなど、相手の母国語で丁寧に状況を説明し、今後の対応について話し合うことが重要です。
これにより、外国人労働者への配慮を示すことで、信頼関係の維持につながります。
外国人労働者を雇用した後のトラブルについて知っておくべきこと
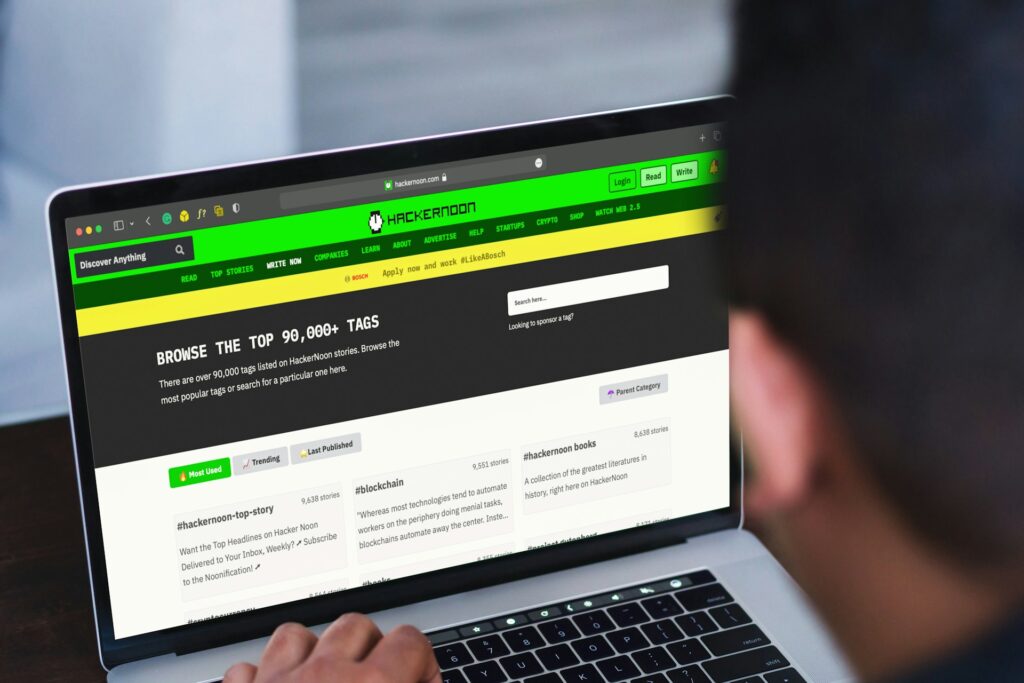
外国人労働者の雇用は、入社手続きが完了すれば終わりではありません。
彼らが日本での生活や仕事に慣れていくなかで、予期せぬトラブルが発生することもあります。
ここでは、雇用後のリスクを回避し、両者が安心して働ける関係を築くための重要なポイントを解説します。
雇用後の予期せぬトラブルと対応の心構え
外国人労働者を雇用した後も、予期せぬトラブルは突然発生する可能性があります。
特に、日本人には当たり前の「民事」と「刑事」の区別が彼らには理解されにくいため、問題がさらに複雑化することがあります。
たとえば、給与の未払いや契約内容の不履行といった問題は民事の領域であり、警察が介入することはありません。一方、暴行や窃盗といった行為は刑事事件として扱われます。
この違いを明確に伝え、万が一トラブルが起きた際にどこに相談すべきかを事前に共有しておくことが非常に重要です。
労働基準監督署や弁護士など、トラブルの種類に応じて適切な相談先があることを知ってもらうことで、問題の早期解決につながり、外国人労働者の安心にも繋がります。
基本的に民事のトラブルは警察に相談できない
職場での外国人労働者とのトラブルが、給与の未払い、契約内容の不履行、人間関係のいざこざなど民事的な問題であった場合、警察に相談しても介入してもらうことはできません。
警察が対応するのは、暴行や窃盗など犯罪行為が伴う場合に限られます。
そのような労働問題に関するトラブルの場合は、まずは社内の担当者や専門の相談窓口に連絡し、労働基準監督署や弁護士など適切な機関に相談することが重要になります。
労働条件に関する問題は労働基準法に基づいており、この法律の専門家である労働基準監督署に相談することが有効です。
外国人労働者雇用問題の現状
近年、日本政府が外国人材の受け入れを積極的に推進していることもあり、外国人労働者の数は増加の一途をたどっています。
しかし同時に、彼らを取り巻く労働環境の問題も顕在化し、ニュースなどで報じられる機会が増えてきました。
特に賃金や労働条件に関する不満や、日本人との文化の違いによるコミュニケーションの壁などが、外国人労働者の定着を難しくしている現状があります。
これらの問題を解決し、外国人労働者が日本で安心して働ける環境を整えることは、日本の労働力不足を補ううえで大きな課題となっています。
外国人労働者雇用のトラブルに関するよくある質問
外国人労働者雇用のトラブルに関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。
Q1. 外国人労働者とのトラブル件数はどのくらいですか?
厚生労働省によると、外国人技能実習生の受け入れ企業に対する監督指導を行った結果、約7割の企業で労働基準関係法令違反が確認されたという報告があります。また近年では相談窓口に寄せられるトラブル相談も増えており、外国人労働者を雇用する上でのトラブル件数が増加傾向にあることがわかります。これらの多くは賃金不払い、長時間労働、そして人権侵害に関するものです。
(出典:厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況」)
H3: Q2. 職場で外国人労働者とトラブルになった場合、警察に相談できますか?
職場でのトラブルが犯罪行為や法律違反に発展した場合、警察に相談することは可能です。しかし、給与の未払い、契約内容の不履行といった民事的なトラブルに関しては、警察が介入することはありません。そのような労働問題に関するトラブルの場合は、まずは社内の担当者や専門の相談窓口に連絡し、労働基準監督署や弁護士など適切な機関に相談することが重要になります。労働条件に関する問題は労働基準法に基づいており、この法律の専門家である労働基準監督署に相談することが有効です。
(出典:e-Gov法令検索 「労働基準法」)
まとめ:外国人労働者と企業が共生するために
外国人雇用におけるトラブルは、多くの場合、事前の準備や丁寧なコミュニケーション、そしてお互いの文化や立場を理解しようとする姿勢で防ぐことができます。
外国人労働者を雇用することは、企業の成長に繋がる大きなチャンスです。
本記事で解説した事例や対策を参考に、外国人労働者と企業双方がより良い関係を築くためのヒントとして役立てていただければ幸いです。
理解と歩み寄りの姿勢を持つことで、外国人労働者との雇用問題は乗り越えられます。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。
電話やLINEでお問い合わせ可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。