外国人雇用に必要な書類とは?契約書の作成ポイントとテンプレート解説
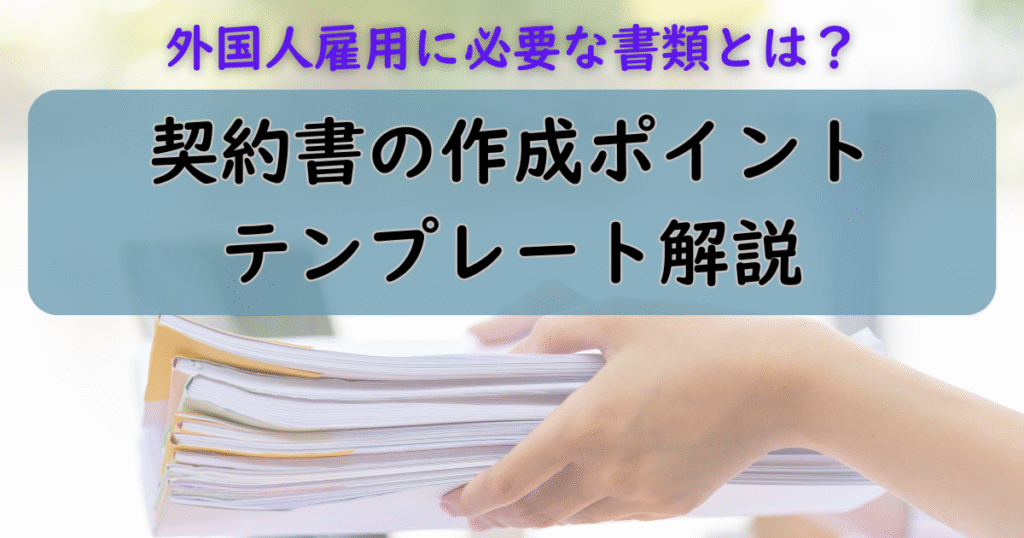
外国人を採用する企業が増えるなかで、採用手続きや契約関連の準備がこれまで以上に重要になっています。
特に初めて外国人を雇う企業にとっては、「何をどの順番で準備すればよいのか」「どんな書類が必要か」といった基本的な疑問が多いのではないでしょうか。
本記事では、外国人雇用に必要な書類や契約書の作成方法、便利なテンプレートの活用術までをわかりやすく解説します。
外国人を雇用する前に確認すべき基本事項
外国人を雇用するには、日本人とは異なる法律や制度への理解が必要です。
違法雇用を防ぐためにも、以下のポイントは最低限押さえておきましょう。
【在留資格の確認】
外国人が日本で就労するには、有効な在留資格が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」「技能実習」など、職種に応じた資格があり、適合しない場合は原則として働けません。
採用時には必ず在留カードの原本を確認し、「就労可」の記載があることを確認しましょう。
【外国人雇用状況の届出】
外国人を雇用・離職させた場合、雇用主はハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があります。
これは雇用対策法に基づくもので、怠ると罰則の対象になることもあります。
外国人雇用に必要な主な書類一覧
外国人を雇用する際には、法的に整備すべき書類があります。
以下に、必要な主な書類を一覧で紹介し、それぞれの役割を説明します。
在留カードのコピー
本人確認と在留資格の確認に必須です。
表裏をコピーし、採用時点と更新時に記録として保管します。
パスポートのコピー
出入国履歴や在留期限を補完的に確認する資料として利用されます。
特に在留期限が近い場合は、更新手続きのサポートも視野に入れましょう。
雇用契約書(または労働条件通知書)
労働基準法に基づき、労働条件を明示する文書です。
外国人の場合は、理解できる言語(英語や母国語など)での作成・併記が推奨されます。
社会保険・雇用保険関連書類
日本国内で働く外国人も、原則として社会保険と雇用保険の加入対象です。
加入手続きには、被保険者資格取得届などの関連書類が必要です。
外国人雇用状況届出書
雇用開始日・在留カード番号・在留資格などを記載し、14日以内にハローワークへ提出します。
雇用契約書の作成ポイント

外国人との契約書は、日本人以上に明確かつ丁寧に作成することが重要です。
以下に、基本的な作成ポイントを示します。
日本語と外国語の併記が基本
外国人が内容を理解できるよう、日本語に加えて英語や母国語の併記が望ましいです。
特に誤解を招きやすい給与や勤務時間、解雇規定などは明確にしましょう。
契約書に記載すべき主な項目
- ●労働契約の期間(例:2025年4月1日〜2026年3月31日)
- ●業務内容(例:翻訳・通訳、介護業務など)
- ●勤務地
- ●勤務時間・休憩・休日
- ●賃金(額・支払い方法・締め日・支給日)
- ●社会保険の有無
- ●解雇・退職に関する取り決め
雇用契約書テンプレートの活用方法
外国人と雇用契約を結ぶ際、内容を一から考えるのは時間も労力もかかります。
そこで役立つのが「雇用契約書テンプレート」です。
あらかじめ決められた書式を活用すれば、基本的な構成を押さえながら、必要事項の抜け漏れを防ぐことができます。
ここでは、テンプレートの活用方法や注意点について詳しく見ていきましょう。
テンプレートを使うメリットとは?
雇用契約書を一から作成するのは大変ですが、テンプレートを活用することで手間を省き、記載漏れを防ぐことができます。
以下のようなメリットがあります。
- 法令に準拠した形式で安心して使用できる
- 必要な項目が網羅されているため、記載ミスや漏れを防げる
- 日本語と外国語の併記がされているテンプレートもあり、外国人にも分かりやすい
無料で使える公的機関のテンプレート
公的機関が提供するテンプレートは信頼性が高く、安心して使えます。
代表的な入手先は以下の通りです。
- 厚生労働省:外国人向けのモデル雇用契約書を掲載
- 外国人技能実習機構(OTIT):技能実習制度に対応した契約書のひな形を提供
- 出入国在留管理庁:特定技能外国人用の契約書テンプレートを公開
実務に合わせたカスタマイズが必要
テンプレートはあくまでも「たたき台」です。
実際の業務内容や就業規則に沿って、以下のような点を調整しましょう。
- ●勤務時間や賃金など、実情に合った数値の入力
- ●深夜勤務や残業に関する条項の追加
- ●業種特有の注意点や安全対策の記載
内容に不安がある場合は、社労士や行政書士などの専門家にチェックを依頼すると安心です。
書類作成後に必要な対応

書類を揃えたあとも、外国人雇用を適正に継続していくには、いくつかの重要なステップがあります
説明・署名、保管管理、就労後のフォローまで一連の対応を怠らないことが、法令順守と信頼関係構築につながります。
外国人人材への説明と署名取得
書類が完成したら、まず外国人人材本人に内容を丁寧に説明しましょう。
契約条件や就業ルールをしっかり理解してもらうことが大切です。
署名・捺印をもらう際には、できれば母国語での説明や通訳を同席させることで、認識のズレを防ぐことができます。
書類の保管と更新
作成した書類は、労基署や入管などの行政機関からの調査や確認に備えて、企業が責任をもって保管する必要があります。
雇用契約書や在留カードのコピーなどは、最低でも3年間保管するのが一般的です。
また、在留資格の更新や契約条件の変更があった場合には、都度書類の見直し・再作成が必要になります。
就労開始後のフォロー
契約後も安心せず、定期的なフォローアップを行いましょう。
業務内容が在留資格の範囲内であるか、賃金や労働時間が契約通りに運用されているかなどを確認します。
問題が発覚した場合は、速やかに改善措置を講じることで、トラブルの未然防止につながります。
よくあるトラブルと防止策
外国人との雇用関係では、日本人とは異なる背景や価値観、法制度への理解の違いなどから、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。
ここでは、実際に起こりやすい事例とその対策を紹介します。
企業が注意すべきポイントを押さえておくことで、長期的かつ円滑な雇用関係の維持につながります。
《トラブル事例1:在留資格外の業務に従事させた》
例:通訳業務として採用したが、実際には営業職を兼務。
→ 防止策:業務内容を明確に定義し、在留資格の範囲内で指示を行う。
《トラブル事例2:言語による誤解で労働条件に不満》
例:休憩時間が十分に与えられていないと訴えられた。
→ 防止策:契約書だけでなく、職場ルールも翻訳・説明し、理解を確認。
《トラブル事例3:保険未加入による行政指導》
例:アルバイト感覚で雇用し、社会保険の手続きを怠った。
→ 防止策:就業形態に関係なく、要件を満たす場合は必ず加入。
まとめ
外国人を雇用するには、多くの書類と手続きが必要ですが、それは外国人人材との信頼関係を築くための土台です。
特に契約書の作成には丁寧さと正確さが求められます。
テンプレートを活用しつつ、実態に即した運用を心がけましょう。
不安がある場合は、社会保険労務士や行政書士など専門家への相談も検討してください。