外国人採用で失敗しない!技能実習と特定技能の5つの大きな違い
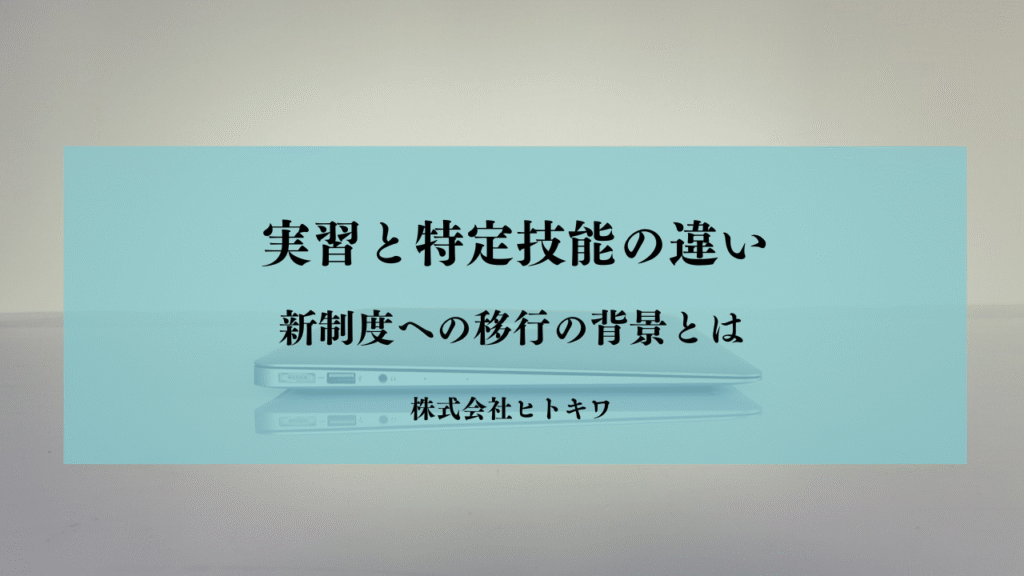
近年、日本の産業界において外国人材の採用と活躍は、持続的な事業運営に不可欠な要素となっています。
技能実習生の制度と特定技能の制度は、日本で外国人が働くための在留資格として広く知られていますが、その目的や仕組みに大きな違いがあります。
それぞれの制度の違いを正しく理解することは、企業が求める人材採用の目的を達成するために必要なことです。
この文書では、技能実習と特定技能の違いを詳細に比較し、外国人材の受け入れを検討している企業が最適な制度を選択できるように、客観的な情報を提供いたします。
「技能実習生」「特定技能」「技人国」の3つの制度を比較し、それぞれの特徴を明確にすることで、企業の採用活動と外国人の日本での業務を円滑化することを目的とします。
技能実習制度とは?その目的と特徴
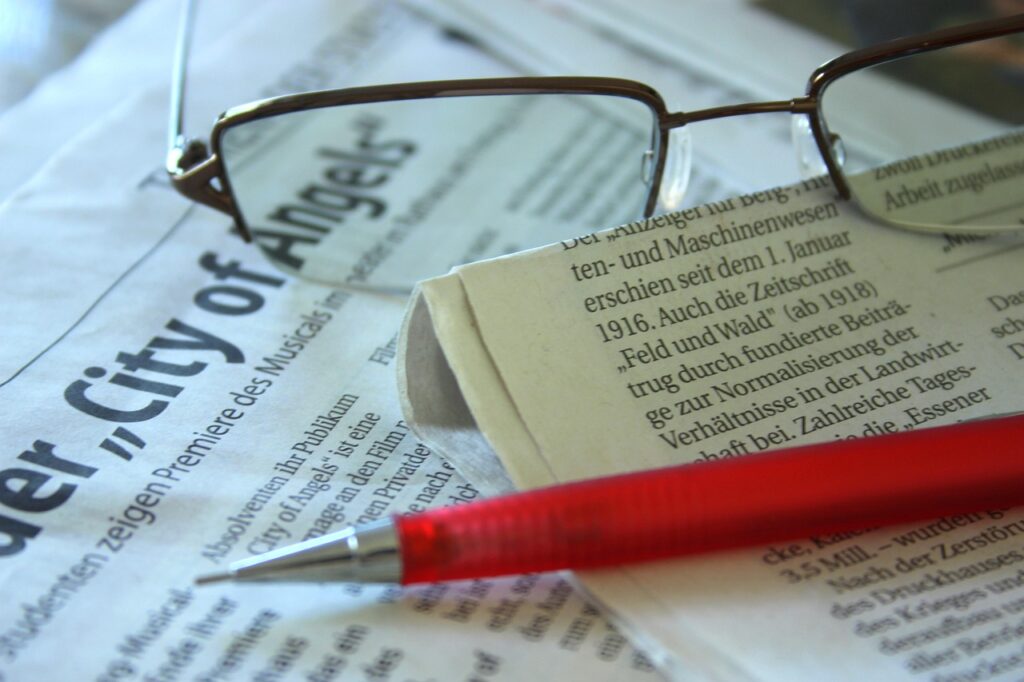
技能実習制度は、特定技能制度とは根本的に目的が異なる、日本の制度です。
この制度は、日本の技能や知識を開発途上国へ移転し、その国の経済発展に貢献することを最大の目的としています。
技能実習生は企業で働きながら技能の習得を目指し、受け入れ企業には、技能を適切に支援し指導する必要がある義務が発生します。
以下に、この制度の具体的な特徴と業務の内容を説明いたします。
① 技能実習制度の目的は国際貢献
技能実習制度の目的は、日本で培われた高度な技能、技術、知識を開発途上国へ移転し、その国の人材育成に貢献することにあります。
この制度の根底にあるのは国際協力であり、外国人労働力の確保はあくまで技能習得の過程で発生する副次的な側面です。
技能実習生は、入国後に行われる講習を経て、定められた職種および業務に従事し、技能の習熟度を高めていきます。
この目的を達成するため、技能実習は技能の習得計画にもとづき、監理団体や企業による厳格な管理下で実施されます。
(参照:外国人技能実習機構「基本理念」)
② 制度の特徴と受け入れ可能な職種について
技能実習制度は、職種や業務が細かく定められており、2024年現在、87職種、159作業が受け入れの対象となっています。
実習は技能実習1号からスタートし、所定の試験に合格することで2号、3号へと移行し、段階的に難易度の高い技能を習得します。
特定技能制度と比べ、企業が独自に技能実習生を受け入れることは難しく、多くの場合、監理団体と呼ばれる非営利団体の支援を必要とします。
この団体は、企業による実習生の技能習得状況や労働環境の監理を定期的に行う必要がある機関です。
③ 実習期間と実習生がたどるキャリアパス
技能実習生が日本に在留できる期間は、技能実習3号まで移行した場合、最長で5年間と定められています。
実習期間を修了した技能実習生は、原則として母国へ帰国し、日本で身につけた技能を活かした業務に従事することが期待されています。
しかし、一定の技能水準を満たした技能実習生は、特定技能1号の在留資格へ移行できる制度が存在します。
この移行は、外国人が日本でより長く技能を活かして働くためのキャリアパスの一つとして機能しています。
特定技能制度とは?就労目的の新しい在留資格
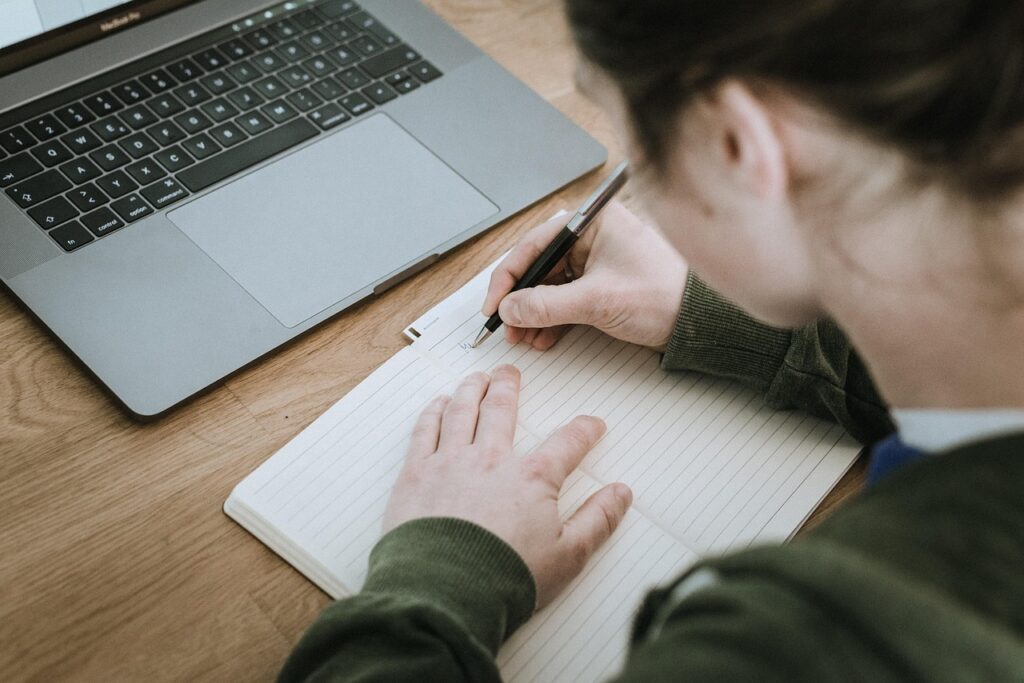
特定技能制度は、技能実習制度と異なり、日本の深刻な人手不足に対応するために目的として創設された新しい在留資格です。
この制度は、特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とし、企業の労働力確保に直接貢献します。
特定技能の外国人は、技能実習生とは違い、労働者として迎え入れられ、日本人と同等以上の賃金を受け取る必要があります。
以下に、この制度の創設背景や、1号と2号の違いを詳細に説明いたします。
① 特定技能制度の創設背景と目的
特定技能制度は、2019年4月に、深刻化する労働人口の減少に対応するために導入された在留資格です。
この制度の最大の目的は、人手不足が特定されている分野において、技能水準および日本語能力試験に合格した外国人を採用し、即戦力として迎え入れることです。
これにより、企業は業務を安定的に継続でき、外国人は日本で安定した労働支援と生活基盤を得ることが可能になります。
技能実習制度が国際貢献を目的とするのに対し、特定技能制度は日本の労働市場の必要性に応える目的を持つ点で、明確な違いがあります。
(参照:外務省「在留資格 特定技能」/法務省「特定技能 ガイドブック」)
② 1号と2号の違いや対象となる産業分野
特定技能の在留資格には、特定技能1号と特定技能2号という2種類があり、在留期間や技能水準、家族帯同の可否に違いがあります。
1号は特定の分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人を対象とし、在留期間は通算5年が上限です。
2号は、特定の分野で熟練した技能を持つ外国人が対象であり、在留期間の上限がないため、永住を視野に入れた日本での長期就労が可能です。
特定技能の採用を検討する企業は、1号と2号それぞれの違いを理解し、業務内容や外国人材の目的に合った在留資格を選択することが必要です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可能) |
| 技能水準 | 相当程度の技能(即戦力) | 熟練した技能 |
| 家族帯同 | 基本的に不可 | 配偶者と子どもの帯同が可能 |
| 日本語能力 | 日常生活や業務に必要な日本語能力が必要 | 試験による高い水準は必要とされない |
| 対象分野 | 12分野 | 介護を除く11分野が対象 |
③ 「介護」分野での特定技能が注目される理由
特定技能の対象分野の中でも、介護分野は特に外国人材の必要性が高く、特定技能制度の活用が積極的に進められています。
介護の業務は、人とのコミュニケーションや専門的な技能を必要とするため、特定技能1号の試験では介護日本語評価試験が別途課されます。
技能実習生として介護業務を3年間経験した外国人は、特定技能1号へ移行することで、技能を活かして最長5年を超えて日本で働くことが可能です。
特定技能の外国人は、企業の直接採用となるため、技能実習のように監理団体を通じた監理費用が発生しない点も、企業にとっては大きなメリットとなります。
技能実習と特定技能の「5つの違い」を徹底比較
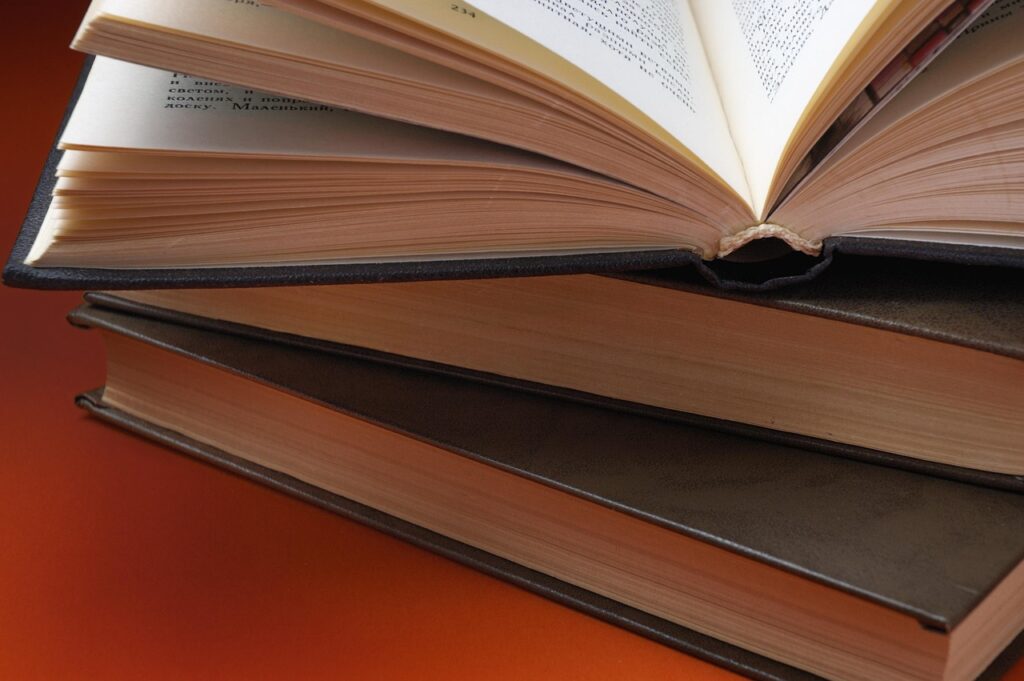
技能実習制度と特定技能制度の違いは、企業の採用計画や外国人材の日本での生活に直結するため、詳細な比較が必要です。
この2つの制度の根本的な相違点を、5つの重要な項目に分けて詳細に説明し、企業の理解を深めることに役立てます。
在留資格の目的、転職の可否、家族帯同の違いなど、実務で重要となる違いを明確に把握することが、適正な外国人採用の鍵となります。
① 制度の根本的な「目的」が大きく異なる
技能実習制度の目的は、国際貢献であり、外国人に技能を習得させ、母国に移転させることが最大の目的です。
対照的に、特定技能制度の目的は、日本の産業界で特定の分野における人手不足を補うことであり、外国人を即戦力とする労働力として採用します。
この目的の違いから、技能実習生は監理団体の監理下に置かれる必要があるのに対し、特定技能の外国人は登録支援機関の支援を受けながら、企業と直接雇用契約を結びます。
企業は、技能実習では「技能移転」を、特定技能では「労働力確保」を主たる目的として制度を活用します。
② 転職の可否や在留期間のルールの違い
技能実習生は、原則として技能習得計画を途中で変更することが認められていないため、受け入れ企業を変更(転職)することはできません。
一方、特定技能1号の外国人は、同一分野内の特定技能を受け入れている別の企業への転職が制度上認められています。
在留期間についても、技能実習は最長5年、特定技能1号も最長5年ですが、特定技能2号は在留期間の上限がないという明確な違いがあります。
外国人材が日本で長期的なキャリア形成を目的とする場合、転職の自由度と在留期間の上限がない特定技能2号が有力な選択肢となります。
③ 家族の帯同に関する制度上の相違点
技能実習生は、技能の習得に専念することが目的であるため、在留期間中に配偶者や子どもなどの家族を日本に帯同させることは原則として認められていません。
これに対し、特定技能1号の外国人も家族帯同は認められていませんが、特定技能2号へ移行した外国人は、家族を日本へ呼び寄せることが可能となります。
家族帯同の可否の違いは、外国人材が日本で永住を含めた長期的な生活設計を検討する上で、非常に重要な要素となります。
企業が特定技能2号の外国人を採用する場合、外国人の家族構成や生活支援体制についても考慮する必要があります。
④ 技能実習修了者が特定技能へ移行する要件
技能実習を2年10ヶ月以上良好に修了した技能実習生は、技能水準および日本語能力の試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。
技能実習生としてすでに日本での業務経験と技能、日本語能力を習得していることが、特定技能の目的である即戦力性の証明となります。
この移行制度は、技能実習生と特定技能の制度が相互に連携していることを示すものであり、外国人材の日本でのキャリア継続を支援します。
企業はこの移行ルートを活用することで、技能を習熟した外国人材を継続的に採用し、業務に活かすことが可能となります。
⑤ 求められる日本語能力や試験の有無
技能実習生は、入国前の講習で基本的な日本語を習得しますが、技能実習の在留資格取得に際し、公的な日本語能力試験の合格は必要とされません。
特定技能1号の外国人は、在留資格を取得するために、業務に必要な日本語能力を証明する試験への合格が必要となります。
ただし、技能実習生から特定技能1号へ移行する場合、日本語能力試験と技能試験の両方が免除されるという違いがあります。
特定技能の外国人は、日本語能力試験の合格が必要なため、企業は特定技能の外国人に対して、より円滑なコミュニケーションを期待できます。
「技人国」との違いを理解して最適な選択を
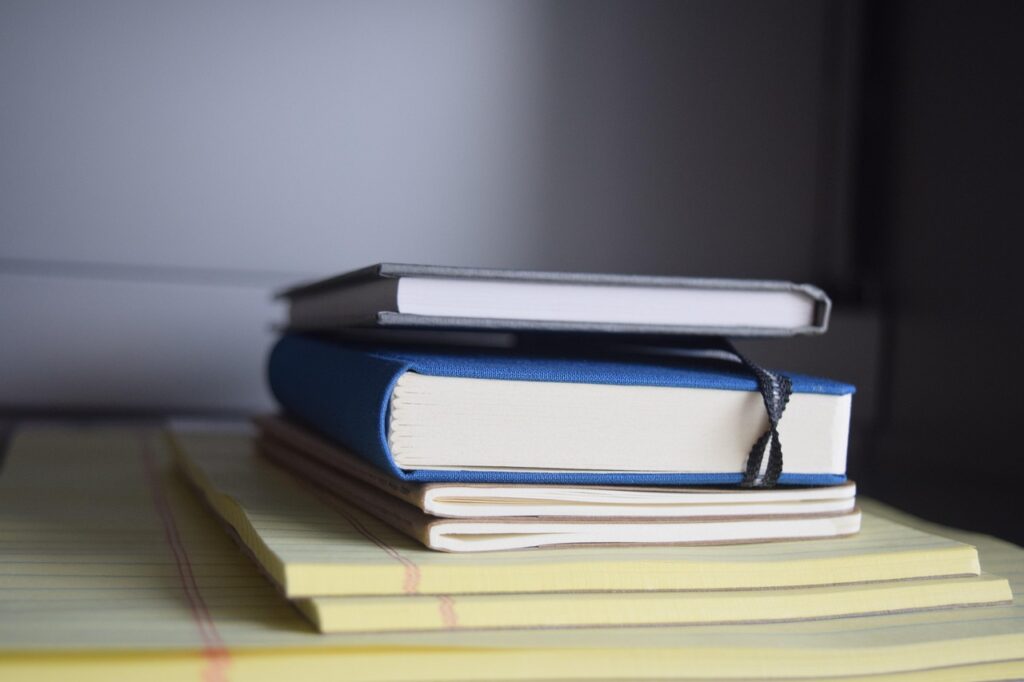
技能実習と特定技能に加えて、「技術・人文知識・国際業務」の略称である「技人国」も、外国人材の在留資格として広く活用されています。
技人国は、技能実習や特定技能とは異なる、高度な専門知識や技術を目的とする在留資格です。
これら3つの制度の違いを理解することで、企業の業務内容に適した外国人材の採用が実現します。
① 技能実習生、特定技能、技人国の目的の違い
技能実習生、特定技能、技人国の3つの在留資格は、日本へ外国人を受け入れる目的が明確に異なっており、この違いが業務内容や在留期間のルールを決定します。
企業は、外国人材にどのような業務を任せたいか、どれほどの専門性を必要とするかを基準に、最適な制度を選択することが必要です。
目的の違いを理解することで、企業が外国人材に提供すべき支援の内容や、採用時に確認すべき試験の有無も明確になります。
以下の表に、3つの在留資格の目的の違いをまとめます。
| 在留資格 | 制度の主な目的 | 求められる技能・知識 |
|---|---|---|
| 技能実習生 | 国際貢献・技能移転 | 比較的簡易な技能の習得 |
| 特定技能 | 日本の人手不足の解消 | 特定分野での即戦力となる技能 |
| 技人国 | 高度な専門性を持つ外国人の採用 | 大卒以上の専門知識・技術 |
② 在留資格「技人国」の要件と高い専門性
在留資格「技人国」は、特定技能の外国人とは違い、高度な専門性を目的とする外国人に付与される在留資格です。
この在留資格の取得には、日本の企業での業務に関連する分野の大学卒業以上の学歴や、10年以上の実務経験が必要となります。 (参照:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」)
特定技能が現場での技能を目的とするのに対し、技人国は業務に関する知識や思考力を活かした専門的な業務を目的とします。
企業が外国人にシステム開発や翻訳、経営企画などの業務を任せたい場合は、技人国の在留資格の外国人を採用することが必要となります。
よくある質問(FAQ)
特定技能制度や技能実習制度の運用に関して、企業から頻繁に寄せられる5つの質問と、それに対する回答をご紹介いたします。
特定技能の受け入れ人数制限や、技能実習生の管理に関する具体的な疑問に答えることで、企業の外国人材採用に関する理解が深まることを目的とします。
在留資格の違いや制度のルールに関する疑問点を解消し、適正な採用と支援体制の構築に役立ててください。
① 特定技能の受け入れ人数に制限はありますか
特定技能1号の外国人の受け入れ人数には制限が設けられており、受け入れ企業が採用している常勤職員の人数が上限となります。
たとえば、企業の常勤職員が20名の場合、受け入れ可能な特定技能1号の外国人は最大20名までという制限があります。
ただし、特定技能2号の外国人の採用については、この人数制限が適用されないため、熟練した技能を持つ外国人を企業が必要とする人数だけ採用できます。
この制限は、日本人労働者の雇用機会に影響を与えないようにするために設けられている制度上のルールです。
② 技能実習と特定技能を同時に利用できますか
技能実習制度と特定技能制度の両方を、1つの企業が同時に活用することは制度上可能です。
企業は、技能実習生に技能を習得させる業務を担当させ、特定技能の外国人に即戦力としての業務を担当させるという役割分担ができます。
それぞれの在留資格の目的と業務内容の違いを明確にし、監理団体および登録支援機関との連携を必要とします。
企業は、技能実習生と特定技能の外国人に対する支援体制を個別に確立し、適切に管理する必要があります。
③ 特定技能の外国人は転職ができますか
特定技能1号の外国人は、同一の産業分野内であれば、特定技能の外国人を受け入れている企業間での転職が認められています。
特定技能制度は、日本の労働力不足解消を目的としているため、外国人の労働支援と自由な業務選択を可能としています。
転職は、外国人本人が出入国在留管理庁に在留資格の変更手続きを行うことが必要であり、企業側も必要な支援を行う必要があります。
技能実習生は原則として転職が認められていませんので、この点に大きな違いがあります。
④ 技能実習生が失踪した場合どうなりますか
万が一、技能実習生が実習期間中に失踪した場合は、受け入れ企業は監理団体と連携し、直ちに出入国在留管理庁へ届け出を行う義務があります。
失踪は技能実習制度の目的である技能移転を達成できなくなるだけでなく、外国人の人権保護にも関わる重大な問題です。
失踪を未然に防ぐため、企業は監理団体と協力し、技能実習生に対して適切な生活支援や日本語学習支援を継続的に行う必要があります。
失踪が発生した場合、企業は今後の外国人受け入れに影響を及ぼす可能性があるため、厳格な管理体制が必要です。
⑤ 技能実習生と特定技能で給料に違いはありますか
技能実習生と特定技能の外国人の給料については、制度上、日本人と同等以上の報酬を支払うことが企業に義務付けられています。
特定技能の外国人は、特定技能の制度の目的である即戦力として、業務内容に見合った適切な水準の給料を受け取ることが必要です。
技能実習生についても、技能実習法にもとづき、企業の同種の業務に従事する日本人労働者と同等以上の給料を支払う必要があります。
したがって、企業が特定技能または技能実習の外国人を採用する場合、日本人との間で不当な賃金格差を設けることは認められていません。
まとめ
技能実習生と特定技能は、どちらも外国人を日本で受け入れるための在留資格ですが、国際貢献を目的とする技能実習に対し、労働力確保を目的とする特定技能という根本的な違いがあります。
特定技能制度は、介護分野をはじめとする特定の産業分野における人手不足の解消に大きく貢献しており、特定技能2号へ移行することで長期的な日本での就労も可能です。
企業が外国人材を採用する際は、在留資格の目的、転職の可否、家族帯同の違いを明確に把握し、自社の業務と外国人の目的に合った制度を選択することが必要です。
また、高度な専門知識を目的とする「技人国」の在留資格も存在しており、企業のニーズに応じて最適な制度を活用することが、外国人材の採用成功と企業の成長に直結いたします。
この文書で提供した情報を活用し、企業の外国人材採用活動を円滑に進めてください。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。