外国人技能実習生の5大問題|失踪・低賃金・借金の原因と解決策
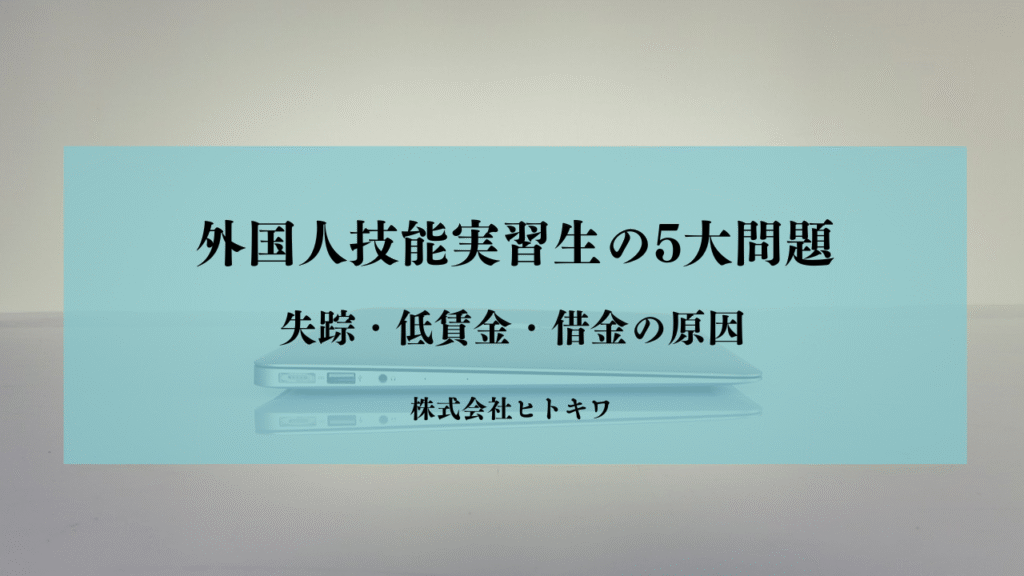
外国人技能実習制度は、開発途上国への技能や知識の移転を通じた国際貢献を目的とする制度として、法務省、厚生労働省、外務省の共管のもと実施されています。
しかし、近年、実習生の方々が置かれている過酷な労働環境や、賃金に関する問題がニュースで発生し、社会的な議論を呼ぶケースがふえています。
実習生の方々が来日後に直面する問題点を正しく理解し、その構造的な原因と具体的な解決策を解説することは、技能実習制度を改善するために必要不可欠です。
この記事では、技能実習生が日本で抱える様々な問題と、企業や団体が取り組むべき対策について、客観的な視点から詳細に述べています。
技能実習生の問題点
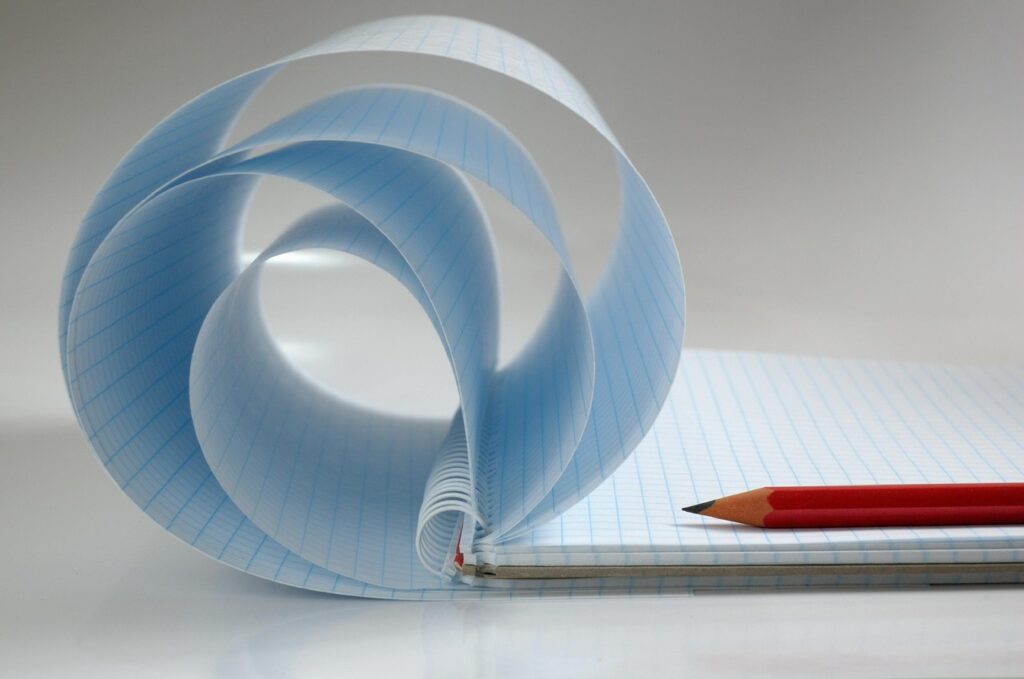
技能実習生の方々が日本での生活や労働環境で直面する問題点は、多岐にわたります。
これらの問題は、個人のトラブルとして片付けられるものではなく、制度の構造的な原因によって発生しているケースが多くあります。
実習生の方々を理解し、真の対策を実施するために、まずは外国人実習生が抱える問題点の核心について解説します。
①期待と現実のギャップから生じる不満
技能実習の問題の多くは、来日前に抱いていた期待と、日本での厳しい現実との大きなギャップから発生しています。
実習生の方々は、来日すれば高収入を得て技能を習得できるという期待をもって日本に来ますが、実際には長時間労働環境や予想よりも低い賃金に直面するケースが少なくありません。
特に、期待していた職種での技能実習が受けられず、単純作業ばかりを強いられるというトラブルは、実習生の方々の学習意欲を低下させる主要な原因です。
このギャップは不満となって問題行動につながる可能性があり、送出し機関や受け入れ企業による正確な情報提供が必要な対策とされます。
②言葉や文化の違いによるコミュニケーションの問題
外国人技能実習生が日本の企業で働く際、言葉の壁は日常的な問題点となり、多くのトラブルを発生させる原因となります。
日本語能力が不足しているため、仕事上の指示や生活上のルールを正確に理解することができず、ささいな行き違いから大きな誤解へと発展するケースがあります。
また、日本の独自のビジネスマナーや生活習慣などの文化の違いも、実習生の方々にとっては大きなストレスや問題意識を抱える原因となることがあります。
企業側は、実習生の方々が安心してコミュニケーションを図れるように、多言語対応のサポート体制を整え、お互いの文化を理解するための研修を実施する必要があると考えられます。
③失踪問題の背景にある複雑な事情
技能実習生の失踪は、技能実習制度の抱える最も深刻な問題であり、その背景には複数の複雑な原因が絡み合っています。
劣悪な労働環境、低すぎる賃金、そして実習先の企業や団体からのハラスメントなど、人権を無視した扱いに耐えきれず逃げ出すケースが多く報告されています。
さらに、母国の送出し機関に支払った多額の借金返済のために、より高い賃金を求めて失踪せざるを得ないという経済的な事情も、失踪を促す大きな原因のひとつです。
失踪を防ぐためには、企業や監理団体が労働条件を改善し、外国人技能実習機構(OTIT)が制度を厳しく監理するといった根本的な対策の実施が必要です。
④心身の健康を脅かす重い負担
技能実習生は、日本での慣れない生活と過酷な労働環境により、心身の健康を損なうという深刻な問題点を抱えるケースがあります。
特に、長時間労働や、十分な休息がとれない状況が続くと、身体的な疲労だけでなく、精神的なストレスも蓄積し、健康被害を発生させる原因となります。
日本語でコミュニケーションをとるのが難しい環境では、問題や体調不良を周囲に訴えることができず、症状を悪化させてしまうトラブルも発生しています。
受け入れ企業は、定期的な健康診断の実施に加え、実習生の方々がいつでも相談できる窓口を設け、心理的なサポートを行うといった対策が必要です。
⑤来日費用と母国での多額の借金
技能実習生の多くは、日本へ来る前に母国の送出し機関に対して高額な手数料を支払い、そのために多額の借金を背負うという経済的な問題を抱えるケースがあります。
この借金は、日本での実習期間中の収入で返済することが前提とされているため、実習生の方々は極めて強い経済的プレッシャーの中で労働環境に身を置くことになります。
仮に日本での賃金が低かったり、劣悪な労働環境に置かれたりしても、借金があるために簡単に帰国や離職を選ぶことができないという問題点が発生します。
この借金問題を解消するためには、送出し機関の不当な手数料請求を規制し、技能実習制度全体の透明性を高める対策が国際的な連携のもと必要です。
技能実習生制度による問題・トラブルの事例

技能実習制度に内在する構造的な問題点は、日本各地でさまざまなトラブル事例を発生させています。
これらの事例は、外国人技能実習生の労働環境がいかに過酷であるかを示しており、制度の目的と実態との間に大きなズレがあることを解説しています。
ここでは、特に社会的に問題視されている具体的なトラブル事例について解説します。
①賃金・労働条件に関するトラブル
技能実習制度における最も頻繁に発生するトラブル事例は、賃金の不払いや不当な労働条件に関する問題です。
実習生の方々には日本人と同等以上の報酬が支払われることが法令で義務付けられています。しかし、実際には最低賃金以下で働かされるといった違法事例や、不当な控除による低収入が報告されています。
また、長時間労働や危険な作業の実施を命じられるなど、技能実習の目的から逸脱した過酷な労働環境に置かれる事例も、問題の原因として指摘されています。
受け入れ企業は、賃金や労働時間の管理を徹底し、法令遵守を最優先するという対策を必要とします。
②人権侵害やハラスメント
技能実習生に対する人権侵害やハラスメントは、制度の深刻な問題点を象徴するトラブル事例のひとつであり、実習生の方々に大きな精神的苦痛を与えています。
具体的な事例としては、暴言や暴行といった身体的・精神的なハラスメントに加え、パスポートや預金通帳を企業側が取り上げるという行為も発生しています。
このような行為は、実習生の方々の自由を不当に奪うものであり、日本の企業が国際的な人権基準を遵守していないという問題を浮き彫りにします。
監理団体は、定期的な実態調査を実施し、実習生の方々からの通報があった際には速やかに対策を講じ、人権侵害を許さない姿勢が必要です。
③制度の目的と実態のズレが引き起こす
技能実習制度は本来、開発途上国への技能移転を目的としていますが、実態は日本国内の労働力不足を補うための外国人労働者採用制度として機能しているという問題点が指摘されています。
この目的と実態のズレが、実習生の方々が技能習得に関係のない単純労働ばかりをさせられるというトラブル事例を発生させる主な原因です。
実習生の方々が希望した職種での技能実習が受けられないケースは、技能実習制度の国際貢献という大義名分を揺るがす重大な問題となっています。
厚生労働省は、技能実習の目的を達成できるよう、実習計画の厳格な審査と、実態を伴わない企業への指導強化という対策が必要です。
④わがままな技能実習生に困らされている
受け入れ企業や監理団体からは、一部の技能実習生が「わがまま」に見える行動をとるというトラブル事例が発生し、問題を抱えているという声も上がります。
しかし、これらの行動の多くは、前述した期待と現実の大きなギャップや、労働環境に対する不満、あるいは文化の違いからくるコミュニケーションの問題が原因であるケースがほとんどです。
実習生の方々が自らの権利を主張したり、不当な扱いに抗議したりする行動が、企業側から見て「わがまま」と誤解されてしまう問題点があります。
企業は、実習生の方々の行動を単なるトラブルとして処理するのではなく、その背景にある原因を深く理解し、対話を通じて解決策を見つけ出すことが必要な対策です。
⑤監理団体による不十分なサポートと指導
技能実習制度において、実習生の方々と企業の間に立ち、適正な実習をサポートする役割を担うのが監理団体ですが、その監理機能の不全が問題点として指摘される事例があります。
一部の監理団体は、実習生の方々の労働環境や人権侵害の問題を把握しながらも、受け入れ企業からの手数料に依存しているために、厳正な指導を実施しないケースが発生しています。
実習生の方々が監理団体にトラブルを訴えても適切な対策がなされず、問題が放置されてしまうという事例は、制度全体への不信感につながる重大な原因です。
法務省・厚生労働省は、監理団体の審査基準を厳格化し、不適切な監理団体に対しては迅速に処分を行うといった対策の実施が必要です。
問題解決に向けた具体的な解決策と取り組み

技能実習生の問題を根本的に解決し、実習生の方々が安心して日本で技能実習に専念できる環境を整備するためには、多方面からの協力と具体的な対策が必要です。
国、企業、監理団体、そして外国人実習生自身が、それぞれの立場で責任を果たし、問題点の解消に向けて取り組むことが解決策の鍵となります。
ここでは、現在実施されている取り組みと、今後さらに強化されるべき対策を解説します。
受け入れ企業に求められる環境整備
受け入れ企業は、技能実習生の問題を解決するための最も重要な主体であり、適正な労働環境の整備が必要不可欠な対策です。
法令遵守は当然として、賃金は日本人従業員と同等以上に設定し、残業代や休日出勤手当の不払いといったトラブルが発生しないよう厳格に管理する必要があります。
また、実習生の方々の健康管理に配慮し、日本語でのコミュニケーションに不安がある外国人のために、多言語での相談窓口を設置するといった対策の実施も重要です。
企業が実習生の方々を一人の大切な仲間として理解し、尊重する姿勢を示すことが、問題の原因を取り除き、良好な技能実習を可能にする解決策となります。
厚生労働省が推進する制度の見直しと強化
技能実習制度の構造的な問題点に対処するため、厚生労働省は制度の抜本的な見直しと強化を推進しており、新たな解決策の導入を実施しています。
人権侵害や不正行為を働く企業や監理団体に対する罰則の強化、そして実習生の方々の保護をより重視した「育成就労制度」への移行が、2024年の法改正で決定しました。
この新しい制度は、技能実習の目的を明確にしつつ、実習生の方々が特定技能の在留資格へ移行しやすくなるよう設計されており、2027年4月1日の施行に向けて問題点の解消が期待されています。(参照:日本経済新聞「外国人材の育成就労制度、27年4月から 政府閣議決定」)
外国人技能実習機構(OTIT)による監理体制の厳格化と、外国人労働者採用の適正化に向けた継続的な取り組みが、日本の国際的な信用を維持するためにも必要です。
実習生の適正な選定と事前教育の徹底
技能実習生の問題やトラブル事例の発生を未然に防ぐためには、実習生の方々が日本に来る前の段階での適切な対策の実施が極めて重要です。
送出し機関は、技能実習制度の目的や日本の労働環境について正確な情報を提供し、借金を負わせるような不正な手数料徴収を行わないという厳格な監理が必要です。
また、実習生の方々に対する日本語や日本の生活習慣に関する事前教育を徹底することで、来日後にコミュニケーションの問題や期待とのギャップによるトラブルを軽減することができます。
実習生の方々が技能実習に対する正しい理解をもち、目標をもって来日できるように支援することが、問題の原因を根本から断つ解決策となります。
よくある質問(FAQ)
技能実習制度や外国人実習生の問題について、企業や一般の方々から頻繁に寄せられる代表的なご質問とその回答を解説します。問題点の理解を深め、今後の対策を検討する際にお役立てください。
技能実習生制度の問題はなぜ改善されないのですか
技能実習制度の問題が完全に解決されない原因は、構造的な複雑さにあります。
日本国内の労働力不足と、国際貢献という制度の目的との間で生じる矛盾が根本にあり、関係する団体や企業の利害が絡み合っているため、対策の実施が遅れるケースがあります。
厚生労働省は制度の見直しを進めていますが、実効性のある監理と、受け入れ側の意識改革に時間がかかるため、問題点の解消には継続的な取り組みが必要です。
実習生が失踪してしまう主な原因は何ですか
技能実習生が失踪する主な原因は、劣悪な労働環境からの離脱と、母国での借金返済の必要性です。
低賃金や長時間労働といった法令違反のトラブル、あるいは人権侵害に耐えきれず、より良い労働環境を求めて失踪に至るケースがほとんどです。
この問題を解決するには、企業が適正な労働環境を確保し、監理団体が実習生の方々へのサポートを強化する対策が必要です。
企業側がトラブルを避けるためにできる対策は何ですか
企業側がトラブルを避けるために実施できる対策は、法令の厳守と実習生の方々への理解促進です。
特に、賃金や労働時間の管理を徹底し、不当な問題が発生しないよう透明性を保つことが重要です。
また、実習生の方々の母国の文化や習慣を理解するための社内研修を実施したり、気軽にコミュニケーションできる環境を整えたりすることで、ささいな誤解によるトラブルの原因を取り除くことができます。
技能実習制度は今後廃止されるのでしょうか
現行の技能実習制度は、その問題点が指摘されていることを受け、厚生労働省などにより廃止され、新しい制度である「育成就労制度」に移行することが決定しました。
新しい制度の目的は、外国人材の育成と確保に焦点を当てており、実習生の方々の転籍の自由度を高めるなど、人権保護を強化する対策が盛り込まれています。
これにより、現行制度の抱える多くの問題の解決策が図られると期待されています。
実習生を受け入れることのメリットは何ですか
技能実習生を受け入れる企業にとってのメリットは、国際貢献への寄与と企業の活性化です。
日本の技能や知識を外国の方々に移転することは、国際社会への貢献という目的達成につながります。
また、意欲の高い外国人材を採用することは、職場の活性化や、日本人従業員の異文化理解を深める原因となります。
人材不足の解消だけでなく、企業のグローバルな視点育成にも必要な機会を提供します。
まとめ
技能実習生制度は、その崇高な目的とは裏腹に、賃金不払いや人権侵害、失踪といった深刻な問題を発生させており、早急な対策が必要です。
これらの問題点の原因は、企業や監理団体の不適切な運営だけでなく、制度自体の構造的な欠陥にもあるという事実を理解する必要があります。
厚生労働省による制度の見直しと、受け入れ企業による労働環境の根本的な改善を実施することが、解決策として求められています。
外国人技能実習生を単なる労働力としてではなく、日本の技能を学ぶ一人の大切な人材として尊重し、国際的な信頼に応える制度へと転換していくことが、日本社会全体にとって必要な取り組みであると解説します。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。