外国人労働ビザの基本を解説|種類・申請方法・注意点までわかりやすく紹介
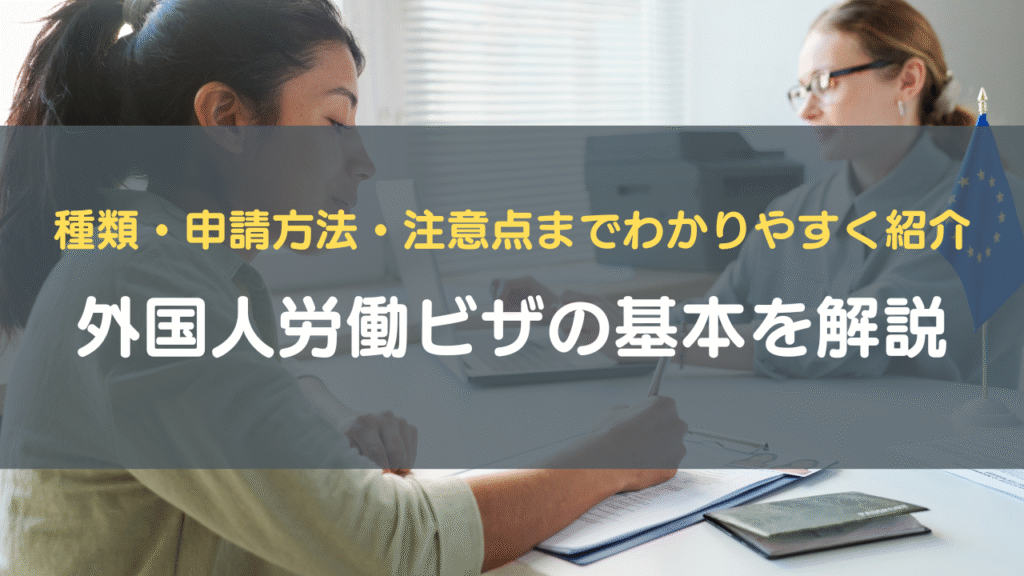
グローバル化が進む中、外国人材の雇用を検討する企業が増えています。
労働ビザの取得は、採用を成功させるための第一歩です。
ビザにはさまざまな種類があり、それぞれの要件や申請手続きが異なります。
事前に基本を理解しておくことで、思わぬトラブルを避け、スムーズな受け入れにつなげることが可能です。
この記事では、外国人労働ビザの種類や申請方法、企業側が押さえるべき注意点を具体的にわかりやすく紹介します。
外国人労働ビザとは
外国人労働ビザとは、外国籍の人が日本で就労するために必要な在留資格の一つです。
別名就労ビザとも呼ばれています。
このビザを取得しなければ、原則として日本で働くことは認められていません。
就労できる内容は、在留資格の種類によって細かく定められており、資格外の業務に従事すると違反となるため注意が必要です。
ここでは、その基本的な定義や働ける範囲について解説します。
労働ビザの定義と特徴
労働ビザとは、外国人が日本で特定の職種に従事するために必要な在留資格の総称です。
単なる「ビザ」ではなく、在留資格ごとに就労内容が明確に定められている点が特徴です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などがこれに該当し、それぞれに求められる学歴や職歴、専門知識が異なります。
一方、「留学」や「家族滞在」などの在留資格では、原則として就労が認められておらず、働くには別途「資格外活動許可」が必要です。
このように、労働ビザとその他の在留資格では、働ける範囲や条件が大きく異なります。
企業が採用を検討する際には、該当する在留資格を正しく見極めることが重要です。
誤ったビザで就労させると、罰則の対象となる恐れもあるため注意しましょう。
外国人が働ける職種・業種
外国人が日本で働ける職種や業種は、取得する在留資格によって厳密に定められています。
単純労働は原則として認められておらず、専門的な知識や技能が必要な職種に限定されています。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では、ITエンジニア、通訳、設計、貿易実務、マーケティング職などが対象です。
また、「特定技能」では外食業、建設業、農業などの分野でも働けます。
これらの資格ごとに求められるスキルや経験、学歴の条件があるため、十分な確認が必要です。
資格に適合しない業務に従事すると、不法就労と見なされるリスクもあります。
主な労働ビザの種類と要件
外国人が日本で働くためには、仕事内容に応じた労働ビザを取得しなければなりません。
労働ビザには複数の種類があり、それぞれ異なる要件や条件が設けられています。
たとえば、高度な専門知識が求められる職種もあれば、一定の日本語能力や実務経験が求められるケースも存在します。
職種や業務内容に合致しないビザを選ぶと不許可となるおそれがあるため、制度の正確な理解が必要です。
ここでは主なビザの種類と要件をわかりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く外国人にとって最も一般的な就労ビザです。
対象となる職種は、ITエンジニア、経理、通訳、マーケティング、貿易実務、商品開発、デザインなど多岐にわたります。
これらの業務は知識や専門性が重視され、工場や現場などでの単純労働は含まれません。
取得には、大学や専門学校を卒業していること、またはそれと同等の実務経験が必要です。
さらに、企業側が提示する仕事内容がビザの要件と一致していることが求められます。
このビザは幅広い分野での雇用に対応できるため、多くの企業に利用されています。
ただし、業務内容と在留資格の適合性が取れていない場合は、申請が却下される可能性があるため、事前の確認が不可欠です。
特定技能ビザ
特定技能ビザは、人手不足が深刻な業種で外国人の受け入れを可能にするために創設された在留資格です。
農業・建設・外食業など14の分野(法務省が定める特定産業分野)が対象となっています。
このビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号では即戦力としての技能と一定の日本語能力が求められます。
試験によってスキルを証明する必要があり、制度に則った雇用契約の締結も条件の一つです。
2号はより熟練した技能者が対象で、家族の帯同や長期滞在も可能となります。
特定技能制度は、技能実習からの移行も想定されており、企業にとっては安定的な労働力確保の手段となります。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザは、ポイント制で評価される制度で、学術・研究・技術分野などの高度人材に向けた在留資格です。
ポイント制によって審査され、学歴・職歴・年収・日本語能力などの項目で一定の点数を満たすことが必要です。
このビザの特徴は、在留期間の優遇や永住申請の短縮、家族の帯同、配偶者の就労許可など、手厚い優遇措置が受けられる点にあります。
また、複数の業務にまたがって活動できる柔軟性も備えており、専門職としての幅広い活躍が可能です。
主に研究者、大学教授、企業の技術開発者などが該当し、日本の経済や技術発展に貢献する人材の受け入れを促進するために設けられました。
企業がこのビザを活用する際は、評価項目を十分に把握し、要件を満たせるような雇用計画を立てることが重要です。
労働ビザ取得と雇用管理の注意点
外国人を雇用する際には、ビザ取得時の手続きだけでなく、雇用後の管理にも細心の注意が必要です。
企業には、在留資格に適合した業務内容での継続的な雇用責任が求められます。
もしビザの種類に合わない仕事を任せると、不法就労と見なされ、企業側にも罰則が科される恐れがあります。
ここでは、労働ビザ取得時とその後の雇用管理における注意点について、わかりやすく解説していきます。
ビザ申請時の書類不備に注意
労働ビザの申請が不許可となる理由の多くは、提出書類の不備や内容の不一致に起因します。
特に雇用契約書や会社概要、職務内容説明書などが不適切だと、審査で不信感を抱かれる可能性が高まります。
申請内容と実際の業務にズレがあったり、企業側の説明があいまいだったりすると、在留資格との整合性が取れないと判断される恐れもあるため、注意が必要です。
また、外国人本人の学歴や職歴が証明できないケースもあるため、注意が求められます。
すべての書類は正確かつ具体的に記載し、指定された形式を厳守する姿勢が求められます。
必要に応じて専門家に相談し、ミスのない申請を心がけましょう。
就労内容の逸脱によるリスク
労働ビザで認められている就労内容は、在留資格ごとに明確に規定されています。
この範囲を逸脱した業務に就かせると、「資格外活動」と見なされ、重大な法的リスクを招く恐れが出てきます。
たとえば、通訳として採用した外国人に倉庫作業を任せた場合、在留資格に適合しないと判断される可能性が高まるため注意が必要です。
企業側には不法就労助長罪が適用されるおそれがあり、罰金や行政処分につながることも。
さらに、本人の在留資格が取り消される事態にもなりかねず、企業と外国人双方にとって大きな不利益となりかねません。
業務内容が変更される際には、在留資格の変更申請を行うなど、適切な手続きを取ることが重要です。
日常的な業務の運用にも注意を払い、制度を正しく守る姿勢が求められます。
更新・変更のタイミングと手続き
外国人労働者を継続して雇用するには、在留資格の更新や変更のタイミングを正しく把握することが欠かせません。
在留期限が切れる前に更新手続きを行わなければ、不法滞在となるリスクがあります。
また、転職や職務内容の変更などがあった場合は、現在の在留資格で対応可能かを確認し、必要があれば『在留資格変更許可申請』を行いましょう。
たとえば、技術職から営業職への異動など、業務内容が大きく変わる場合は、現在の在留資格で対応できるか事前に確認が必要です。
更新や変更の手続きには時間がかかるため、早めの準備が不可欠です。
まとめ
外国人労働ビザの適切な取得と管理は、企業にとって非常に重要な責務です。
正しい手続きを踏み、継続的な確認を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
ただし、実際の申請業務は複雑で、法改正や審査基準の変更にも柔軟に対応する必要があります。
社内だけでの対応が難しい場合には、専門知識を持つ外部サービスの活用が有効です。
ビザ申請から採用後の管理まで一貫してサポートしてくれる「ヒトキワ」のようなサービスを利用することで、企業はより安心して外国人材の受け入れを進められるでしょう。