外国人ビザの更新・変更手続きとは?企業担当者が押さえておきたい基礎知識と注意点
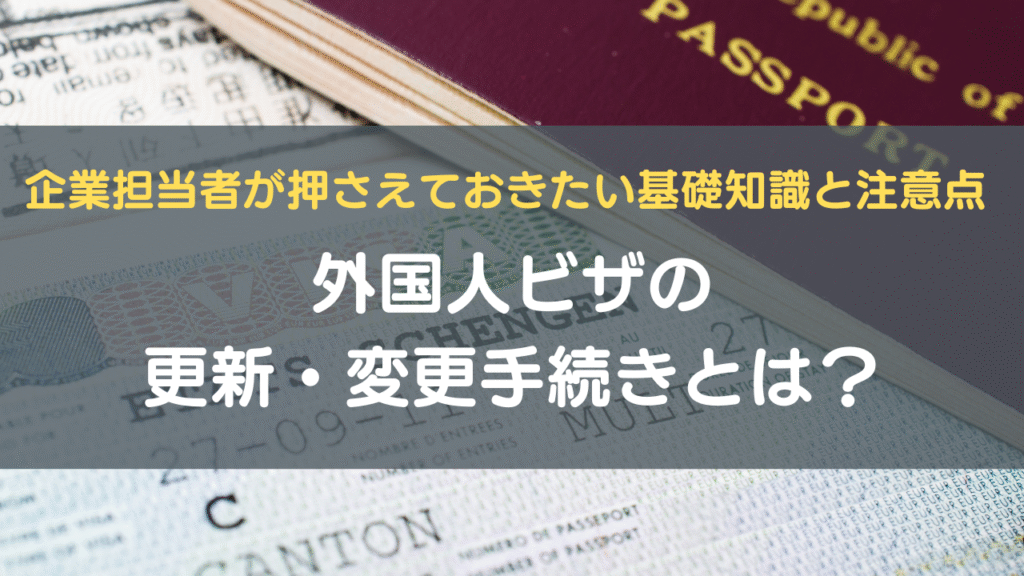
外国人を雇用している企業にとって、在留資格の更新や変更手続きは避けて通れない業務です。
適切な手続きを怠ると、在留資格の失効や不法就労につながる恐れもあるため注意が必要です。
とくに契約更新や部署異動など、雇用内容に変更が生じた際には、速やかに対応しなければなりません。
本記事では、外国人スタッフの継続雇用や職務内容の変更が発生する場合に押さえておきたい、ビザの更新・変更手続きの基礎知識をご紹介します。
外国人ビザの「更新」と「変更」の違いとは?
ビザの手続きには、「更新」と「変更」では適用される状況が異なるため、その違いを正確に理解しておく必要があります。
更新は現在の在留資格のまま在留期間を延長する手続きで、原則として期限の3か月前から申請が可能です。
一方で変更は職種や活動内容が変わる場合に行うもので、タイミングや必要書類も異なります。
状況に応じた正しい手続きを把握することが、企業にも本人にも不利益を避けるうえで欠かせません。
ビザの「更新」手続きとは
ビザの「更新」手続きとは、現在と同じ在留資格で引き続き日本に滞在したい場合に必要な手続きです。
たとえば、外国人スタッフが同じ会社・職務内容で雇用契約を継続するケースが該当します。
在留期限の3か月前から申請でき、出入国在留管理庁に提出する書類としては、在留資格更新許可申請書、パスポート、在留カード、雇用契約書、住民税の納税証明書などが挙げられます。
審査では、就労状況の継続性や生活の安定性が見られ、条件を満たしていれば更新が許可される仕組みです。
なお、申請中に在留期限を迎えた場合でも「特例期間」により引き続き在留できますが、更新申請自体を忘れると不法滞在となるリスクがあるため、早めの対応が重要です。
ビザの「変更」手続きとは
ビザの「変更」手続きとは、転職や部署異動などで在留資格に基づく活動内容が変わる場合、もしくは現状のビザからほかのビザに変更するときに必要な申請です。
たとえば、営業職からエンジニア職へ転職する場合や、別業種へのキャリアチェンジを行うケース、特定活動ビザから技術・人文知識・国際業務ビザなどにに変更するケースが該当します。
この手続きでは、在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード、新たな雇用契約書、職務内容を説明する資料などを整え、出入国在留管理庁の地方出入国在留管理局に提出します。
新しい業務内容が申請予定の在留資格に適合しているかをはじめ、本人の能力や職務経験、生活の安定状況なども総合的に判断される仕組みです。
変更が認められないまま就労を続けると不法就労とみなされるため、企業担当者は早めの確認と手続きが欠かせません。
ビザ更新・変更の手続きの流れと必要書類
ビザの更新や変更を行う際は、必要書類の準備と申請期限の厳守が重要なポイントとなります。
手続きを円滑に進めるためには、全体の流れを事前に把握し、抜けのない準備が重要です。
特に企業側が代理申請を行う場合は、関係書類の整備や提出スケジュールの管理が不可欠です。
雇用している外国人スタッフのエクセル一覧を作成するなどで期限の管理はしっかりと行いましょう。
書類不備や申請の遅れは審査に影響する恐れがあるため、早めの準備が大切です。
本章では、更新・変更手続きの流れと必要書類についてわかりやすく解説します。
更新・変更手続きの基本的な流れ
ビザの更新・変更手続きは、申請から許可まで複数の段階を踏む必要があります。
はじめに、在留資格や活動内容に応じて必要書類を準備しなければなりません。
その後、出入国在留管理局へ書類を提出し、申請を行うことになります。
審査では、活動内容が適切かどうかや書類の整合性が厳しく確認されます。
通常、申請内容や地域により異なりますが、通常1〜3か月程度かかるとされています。
場合によっては追加の資料提出を求められることもあるでしょう。
すべての審査が完了すると、許可通知というはがきが届き、それをもって申請した出入国管理局へ行くと新たな在留カードが発行される流れです。
手続きには時間がかかるため、審査期間を見越したうえで、計画的に進めましょう。
企業側もスケジュール管理を意識し、申請漏れを防ぐ体制づくりが求められます。
よく求められる提出書類の例
更新・変更手続きでは、企業担当者が準備すべき主要書類がいくつかあります。
まず、申請書。
次に雇用契約書では、職務内容や給与、雇用期間などを明記し、変更後の条件が分かるようにしましょう。
さらに、事業内容説明書では企業の業種や業務内容を記載し、外国人の職務が企業活動に合理的に結びついていることを示す必要があります。
職種によっては、技術系なら業務内容の詳細や資格証明書、研究職の場合は研究計画書、その他専門職には業務内容証明書など、業種に応じた資料が必要になることがあります。
次に本人の収入が証明できる書類や納税証明書。
最後に会社の情報が書かれた書類になります。
こうした書類を過不足なく準備すれば、審査官に対して活動の目的や企業との関係性を明確に伝えやすくなり、許可取得の可能性を高められるでしょう。
更新・変更時の注意点と不許可を防ぐための対策
ビザの更新や変更を行う際、不許可となるリスクを避けるには、制度への正確な理解が不可欠です。
企業としても、外国人本人に任せきりにせず、サポート体制を整えることが求められます。
ここでは、不許可を回避するために押さえておきたいポイントや注意点について、わかりやすく解説します。
変更理由の説明不足に注意
変更理由の説明が不十分だと、審査官に活動内容の合理性が伝わらず不許可リスクが高まります。
例えば、営業職からエンジニア職へ転職した場合、単に仕事内容が変わることだけを申告しても不十分です。
なぜこの転職が必要なのか、どうして前職ではできず、今回の職種でどのように企業に貢献できるのかを明確に示す説明書や業務フロー図、個人のスキルや資格を記載した資料などが求められます。
また、変更前後の雇用契約書、仕事内容の詳細がわかる職務記述書を添付することも重要です。
理由の説明が曖昧だと「この活動のための在留資格ではない」と判断されたり、書類に矛盾が見つかったりして不許可となる恐れがあるため、企業担当者としては説明資料の精度を高め、根拠をしっかり準備しましょう。
在留期限の管理と早めの準備
在留期限ギリギリの申請は、予期せぬトラブルを招くことがあります。
余裕を持ったスケジューリングが安全な手続きの基本です。
在留期限の3か月前には更新・変更ができるとはいえ、書類の準備・社内調整・審査期間も考慮し、少なくとも期限の1~2か月前には申請できるよう動きましょう。
期限直前で提出すると、不備発覚時に対応期間が短く、不許可や「不法就労」扱いされるリスクが高まります。
加えて、提出後の審査中に追加書類を求められるケースもあるため、社内と本人の連携が重要です。
不許可になった場合の対応策
ビザの更新・変更申請が不許可となった場合でも、迅速かつ適切な対応で再チャレンジする方法があります。
まず、不許可通知に記載された理由を詳細に確認しましょう。理由に応じて、不足書類や説明不足であれば再申請が可能です。
その際、追加資料や具体的な業務内容、制度要件への適合性を補強すると効果的です。
また、再申請せず異議申し立てを選ぶケースもあります。
異議申し立ては、審査結果通知を受け取ってから14日以内に、所定の書面で異議申立てが可能です。
ただし、すべての申請において異議申立てが認められるとは限りません。
その間も在留資格は有効ではないため、別途在留資格維持の措置(仮滞在許可や特定活動ビザなど)の申請を検討する必要があります。
不許可となった場合は、法務専門家と連携し、再申請や異議申立てと並行して在留維持措置を進められる体制をあらかじめ整えておきましょう。
まとめ
外国人ビザの更新や変更には、制度を正しく理解し、状況に応じた手続きを行うことが重要です。
申請ミスや対応の遅れは不許可の原因となるため、企業側の積極的なサポートが欠かせません。
とくに在留期限の管理や変更理由の説明など、細かな対応が求められる場面も多くあります。
企業が主導して支援体制を整えることで、外国人スタッフも安心して働き続けることができます。
「ヒトキワ」では、こうした課題に対応するビザ申請支援サービスを提供中です。詳しくは「ヒトキワ」公式ホームページをご確認ください。