はじめてでもわかる外国人ビザの基礎と種類|在留資格の違いや取得の流れを解説
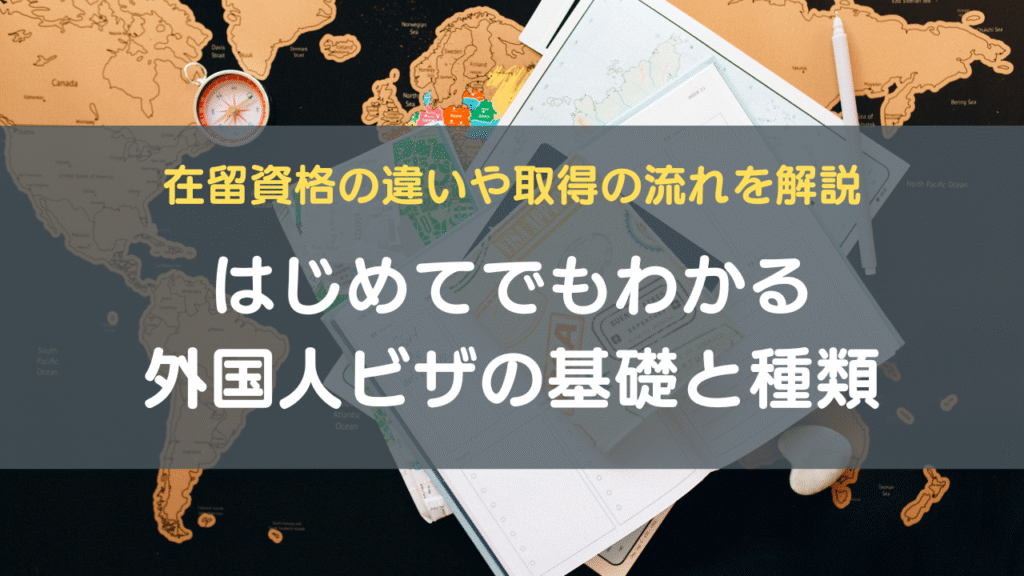
外国人の雇用や受け入れを検討している企業にとって、在留資格(ビザ)の理解は重要です。
ビザの種類や取得条件を正しく把握しておくことで、スムーズな採用や受け入れが可能です。
この記事では、外国人ビザの基本や在留資格の違い、申請、発行の流れを初心者にもわかりやすく解説します。
外国人ビザ(在留資格)の基本を理解しよう
外国人ビザとは、日本に在留するために必要な「在留資格」のことです。
この資格によって、外国人が日本でどのような活動を行えるかや、どれくらい期間滞在できるかが決まります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」など、目的に応じて多くの種類が存在します。
まずはこの制度の基本を押さえ、後の手続きや選定に役立てていきましょう。
知識を持つことで、働いてよいビザなのかの判断にも役立つでしょう。
外国人ビザと在留資格の違いとは
「ビザ」と「在留資格」は似たような意味に思われがちですが、それぞれ異なる役割を担っています。
ビザは、外国人が日本に入国するために必要な“入国許可の推薦状”のような役割を持ち、日本の在外公館(大使館や領事館)が発行するものです。
一方、在留資格は入国後に日本でどのような活動を行うかを定める法的な資格で、出入国在留管理庁によって認定されます。
つまり、ビザは「入国のため」、在留資格は「滞在・活動のため」に必要となります。
この違いを理解していないと、手続きのミスや不備につながる可能性もあるため、最初にしっかり区別しておくことが大切です。
ビザの役割と発給の目的
ビザの役割は、出入国管理の観点から「この外国人は日本に入国しても問題ない」と日本政府が判断した証として機能する点にあります。
日本の在外公館(大使館・領事館)が発給するものであり、入国前に必要とされる重要な書類です。
ビザには観光、ビジネス、就労、留学などさまざまな種類があり、日本での活動目的に応じたビザが発給されます。
たとえば、外国人を雇用する場合には「就労ビザ」に該当するものが必要です。
発給の際には、活動内容や滞在期間、必要書類などをもとに厳格な審査が行われます。
ビザは入国そのものの可否を判断するための手段であり、在留資格とは異なる役割を果たしている点を理解しておきましょう。
在留資格の種類と対象となる活動
在留資格は、外国人が日本で行う活動内容によって分類されています。
たとえば、就労、留学、文化活動、家族滞在など、それぞれの目的に応じた資格が設けられており、内容によって取得条件や活動の制限が異なります。
適切な在留資格を選ぶことは、本人が安心して暮らし、働くために欠かせません。
企業側にとっても、法令に沿った雇用を行うための基本的な知識となります。
ここでは、主な在留資格とその対象となる活動について整理してご紹介します。
技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での就労を目的とした代表的なビザ、通称「技人国」と呼ばれています。
大学卒業やそれに準ずる学歴、あるいは一定の実務経験を有する外国人が対象で、ITエンジニア、設計、通訳、翻訳、語学教師、貿易業務、マーケティング業務など、専門的な知識やスキルを必要とする職種に就くことが可能です。
このビザは単純労働を目的とする活動には適用されないため、業務内容が基準を満たしているかどうかが審査の大きなポイントとなります。
雇用契約を結ぶ企業には、仕事内容や報酬が適正であることを示す書類の雇用契約書や就業条件明示書が必要です。
さらに、仕事内容や所属する会社などの内容に変更が生じた際は、出入国在留管理庁への届出が義務付けられており、企業側にも継続的な管理と制度理解が欠かせません。
特定技能・技能実習などの受入れ制度
「特定技能」および「技能実習」は、日本の現場作業を含む職種で多く導入されている外国人受け入れ制度です。
技能実習は、発展途上国からの人材に対して、技術や知識を習得し、母国を発展させることを目的とする制度であり、建設業や農業、介護などが中心となります。
一方、特定技能は即戦力の外国人材を対象とし、14の産業分野で人手不足を補う目的で設けられました。
特定技能は、一定の日本語能力や業務スキルを有する人材に付与される在留資格であり、一部の分野では、技能実習から特定技能への移行も認められています。
特定技能1号は通算5年までの滞在が認められ、2号では家族の帯同や長期在留も可能になります。
受け入れ企業には、試験の実施や生活支援、就労環境の整備といった責任が求められ、在留資格の制度に乗っ取った運用が重要です。
配偶者ビザや永住権などの居住系ビザ
「配偶者ビザ」や「永住者」などの居住系ビザは、就労制限がなく、日本社会への定着を前提とした在留資格です。
たとえば、日本人や永住者と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、また長期間の滞在実績や一定の収入がある外国人が対象となる「永住者」があります。
配偶者ビザは、家族関係を根拠に在留が認められます。また、上記の「技術・人文知識・国際業務」とは違い、就労活動も制限なく自由に行うことが可能です。
一方、永住権を取得すると在留期間の制限がなくなり、住宅ローンや各種行政手続きにおいても優遇されるケースがあります。
企業が採用を検討する際は、自社の業務内容がどのビザに当てはまるのかを確認しておくとよいでしょう。
さらに、更新条件や必要書類を事前に把握しておくと、対応もスムーズに進められます。
外国人ビザ取得の流れと必要な手続き
外国人ビザを取得するには、大まかな手順と注意点をあらかじめ理解しておくことが大切です。
まず、該当する在留資格を確認し、必要書類を整えたうえで「在留資格認定証明書交付申申請」という申請を行います。
提出先は日本の在外公館または出入国在留管理庁で、審査には1か月以上かかることもあります。
追加資料の提出や面接を求められる場合もあるため、事前準備が欠かせません。
書類の不備や内容の誤りは審査遅延の原因になるため、正確な対応が求められます。
ここでは取得の流れと注意点を、わかりやすくご紹介します。
在留資格認定証明書の申請と交付
在留資格認定証明書は、入国ビザ取得の前提となる重要書類で、主に企業または本人が出入国在留管理庁に対して申請します。
申請先は、外国人が日本での活動地域を管轄する地方出入国在留管理局です。
必要書類には、申請書、パスポートの写し、写真、雇用契約書や業務内容を示す紹介状、学歴証明などが含まれます。
またビザによってはこれから勤務予定の会社の会社案内、全部事項証明書、決算報告書なども求められます。
書類は正確かつ最新の情報でそろえる必要があり、特に雇用契約書は賃金、業務内容など細かく見られます。
申請から交付までは通常1〜3か月を要するため、逆算して余裕を持った準備が必要です。
交付された在留資格認定証明書を用いて在外公館でビザ申請を進める流れとなっております。
入国後の在留カード取得と管理の義務
入国後、外国人は在留カードを取得し、日本での滞在中に常に携帯しなければなりません。
在留カードは、原則として空港の入国審査時にその場で交付されます。
カードには氏名、在留資格、在留期間などの情報が記載されており、更新期限にも注意が必要です。
在留期間の延長や資格変更が必要な場合は、在留期限の3か月前から申請可能です。
企業としては、従業員の在留カードの内容を確認し、在留期限と更新許可申請のタイミングを把握しておく義務があります。
また、氏名や住所の変更がある場合は、14日以内に市区町村役場へ届け出ることが求められます。
まとめ
外国人の受け入れにはビザと業務内容の関係、申請までの流れといったビザや在留資格に関する正確な理解と十分な準備が不可欠です。
制度を正しく把握して手続きを行うことが、トラブルを未然に防ぐための鍵となります。
「ヒトキワ」では、ビザ取得のサポートから人材紹介までを一括で提供し、企業の負担を軽減しながらスムーズな受け入れ体制を提供できます。
外国人雇用を安心して始めたいと考える企業にとっては、まず専門家に相談することが、確実かつ効率的な導入への近道と言えるでしょう。