【2025年最新版】外国人雇用の始め方|ハローワーク活用と協議会の役割を解説
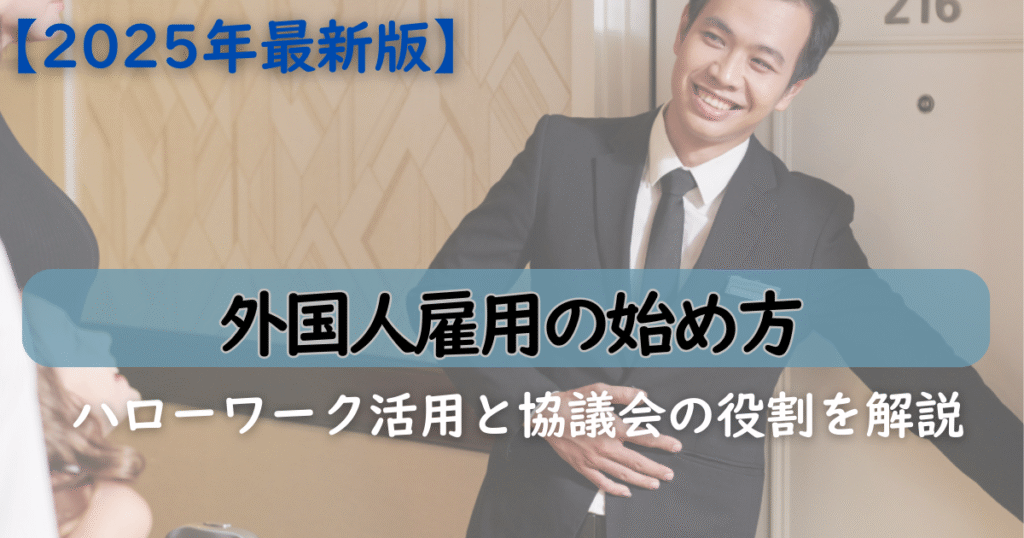
外国人の雇用がますます注目を集めるなか、採用活動や雇用手続きをどのように進めればよいか悩む企業担当者も多いのではないでしょうか。
中でも「ハローワークの活用方法」や「外国人雇用協議会の役割」は、初めて外国人材を採用する企業にとってわかりにくいポイントです。
本記事では、外国人雇用において重要な機関であるハローワークの利用方法と、外国人雇用協議会との関係についてわかりやすく解説いたします。
2025年の最新情報を踏まえ、実務に役立つ内容をお届けします。
外国人を雇用する際の基本【5ステップ】

外国人を雇用する際は、以下のステップに沿って準備を進めていくことが重要です。
各手順を明確にし、ミスなく進めることでトラブルを未然に防ぐことができます。
【ステップ1:在留資格の確認】
外国人が日本で働けるかどうかは「在留資格」によって決まります。
必ず在留カードを確認し、予定している仕事内容がその資格に該当しているかをチェックしましょう。
【ステップ2:雇用条件の整備】
労働時間や報酬、休日などの雇用条件を明文化し、日本人社員と同様に公正な基準で設定することが求められます。
あわせて、就業規則や安全衛生に関する説明も行いましょう。
【ステップ3:雇用契約書・労働条件通知書の作成】
外国人にもわかりやすい形で契約内容を提示することが重要です。
可能であれば英語ややさしい日本語で併記し、誤解が生じないようにしましょう。
【ステップ4:労働保険・社会保険の手続き】
雇用保険・健康保険・厚生年金保険など、必要な社会保険への加入手続きを行います。
手続きの内容は日本人雇用時と基本的に同様です。
【ステップ5:雇用後の届出(ハローワーク・入国管理局など)】
外国人雇用状況届出(ハローワーク提出)や、在留カードの確認記録保管など、法律に基づく提出・保存義務があります。
電子申請には「GビズID」を利用することで、オンラインでの手続きも可能です。
期限を守って確実に対応しましょう。
外国人雇用とハローワークの関係

ハローワークは、外国人の雇用に関しても重要な役割を果たす行政機関です。
ここでは、その具体的な関与内容について解説します。
ハローワークにおける外国人の求人登録方法
ハローワークに求人を出す際、外国人労働者を対象とするかどうかを明記する必要があります。
「外国人可」と表示することで、就労可能な在留資格を持つ求職者にも情報が届きます。
外国人を対象とする場合は、以下の点に留意しましょう。
- ●業務内容が就労可能な在留資格に該当しているか
- ●求人票に必要な言語レベルやスキルを明記する
- ●雇用形態(正社員・契約社員など)や待遇を正確に記載する
外国人労働者の雇用状況届の提出義務
外国人を雇用・離職させた場合、雇用主は「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
これは雇用保険の加入有無にかかわらず必要な手続きです。
- 提出先:所轄のハローワーク
- 提出期限:雇用・離職から14日以内
- 提出様式:様式第3号(厚生労働省指定)
提出を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性もありますので、必ず期限内に届け出ましょう。
雇用後のハローワークからの支援
外国人の雇用後も、ハローワークは企業や従業員の支援を継続的に行っています。
主な支援内容を以下の表にまとめました。
| 支援内容 | 概要 |
| 定着支援・職場環境整備のアドバイス | 異文化理解・トラブル防止・就業継続のためのアドバイスを提供 |
| 外国人向け研修情報の提供 | 日本語学習や就業マナー、安全衛生に関する外部研修などを紹介 |
| 助成金制度の案内 | 外国人雇用に関連する各種助成金の種類・要件・申請方法について情報提供 |
| 通訳付き相談窓口(場合により) | 外国語対応可能な職員や通訳サービスを通じた相談支援(対応言語は地域によって異なる場合があります) |
これらの支援を活用することで、外国人雇用の安定と職場全体のスムーズな運営につながります。
必要に応じて、早めにハローワークへ相談することをおすすめします。
外国人雇用協議会とは?役割と活動内容
外国人雇用協議会とは、地域の行政・経済団体・企業・教育機関・専門家などで構成され、外国人の受け入れと定着支援に取り組む協議体です。
協議会の目的と構成
外国人雇用協議会は、地域で外国人労働者を円滑に受け入れ、安心して働ける環境を整備することを目的とした組織です。
以下の表に、主な目的とその内容をわかりやすくまとめました。
| 目的 | 内容 |
| 情報共有 | 外国人受け入れに関する制度や運用方法、課題などを行政・企業間で共有 |
| 環境整備支援 | 労働条件や生活環境の改善に関する取り組みを支援(例:多言語マニュアル、住宅支援) |
| 多文化共生の推進 | 地域社会と外国人との円滑な共生を目指し、異文化理解の促進や地域イベントなどを実施 |
これらの取り組みにより、企業・地域・行政が一体となって持続可能な外国人雇用の実現を目指しています。
特定技能制度の運用においても、協議会との連携が重要視されています。
地域ごとに設置されており、管轄する行政機関に問い合わせると情報が得られます。
企業が協議会と連携するメリット
外国人雇用協議会と連携することで、以下のようなメリットがあります。
- ●外国人材受け入れの最新情報が得られる
- ●国・自治体の支援制度を活用しやすくなる
- ●企業間での情報交換や課題共有ができる
- ●労務管理や研修体制に関するアドバイスを受けられる
企業単体では解決しづらい課題も、協議会を通じた連携でスムーズに対応できるようになります。
よくある質問と注意点
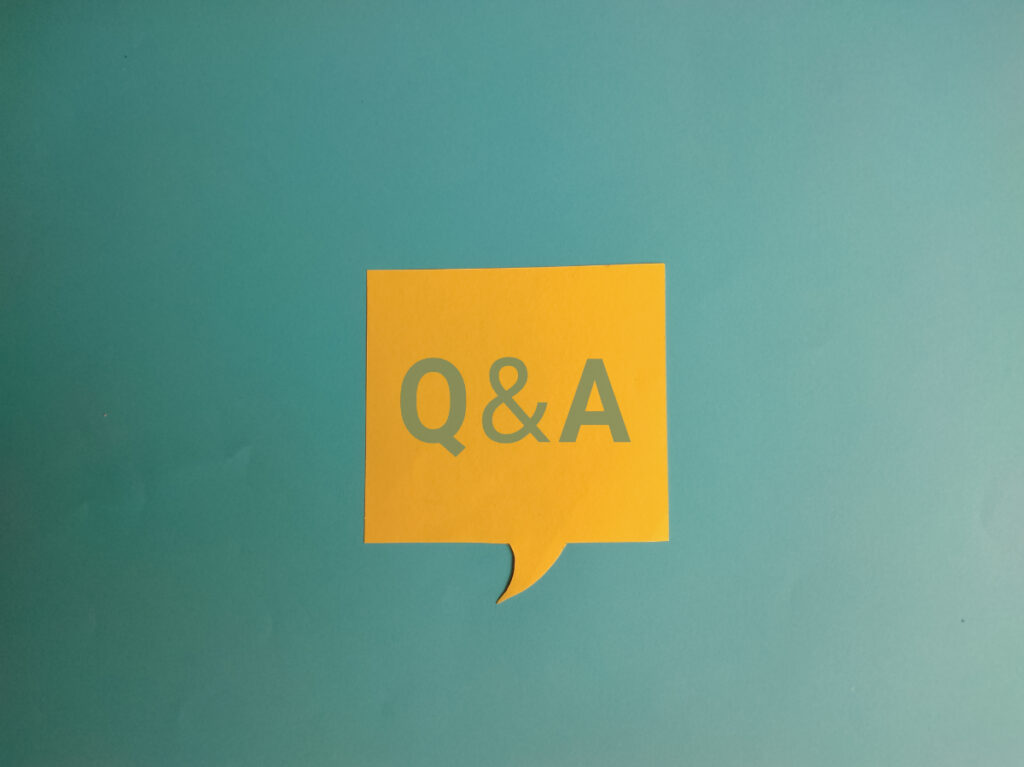
- Q:外国人の求人を出すには、ハローワークを通さなければいけませんか?
- A:民間の求人媒体でも構いませんが、ハローワーク経由だと助成金制度や相談支援を受けやすいという利点があります。
- Q:協議会に参加するのは義務ですか?
- A:義務ではありませんが、特定技能制度を活用する場合は参加を求められることがあります。
- Q:届出を忘れた場合、どのような罰則がありますか?
- A:正当な理由がない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- A:正当な理由がない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
外国人雇用に取り組む企業が今から始められる準備とは
外国人の雇用に関する制度や機関について理解を深めたら、次に取り組むべきは社内体制の見直しと実務の準備です。
特に以下のような対策を講じることで、外国人雇用のスタートをよりスムーズかつ効果的に行うことができます。
- ●受け入れ体制の整備:外国人社員が安心して働けるよう、相談窓口や研修制度、労働条件の整備を進めましょう。
- ●情報の一元管理:在留資格や雇用状況届の提出スケジュール、ハローワークや協議会との連絡履歴など、重要情報を社内で一元的に管理する仕組みを導入しましょう。
- ●法制度の定期チェック:外国人雇用を取り巻く制度は毎年見直されることがあります厚生労働省(外国人雇用対策ページ)や出入国在留管理庁(公式サイト)の情報を定期的に確認することが大切です。
- ●外部との連携強化:行政書士や社労士などの専門家、地域の協議会、商工会議所などと連携を取りながら、制度や助成金活用のアドバイスを得ましょう。
このような社内外の備えを意識することで、制度を最大限に活用し、外国人材の定着と戦力化を図ることが可能となります。
まとめ
外国人を雇用する際には、ハローワークと外国人雇用協議会という2つの機関を正しく活用することが重要です。
ハローワークは求人登録や雇用状況届の窓口であり、制度的な支援が受けられます。
一方で、協議会は地域ぐるみの支援体制を構築する役割を担い、企業にとってのネットワークやサポート源となります。
初めて外国人を雇用する企業様も、これらの機関と連携しながら制度を活用することで、安心・安定した雇用環境を実現できるでしょう。