【外国人労働者関連の法律】法律改正や対策も解説
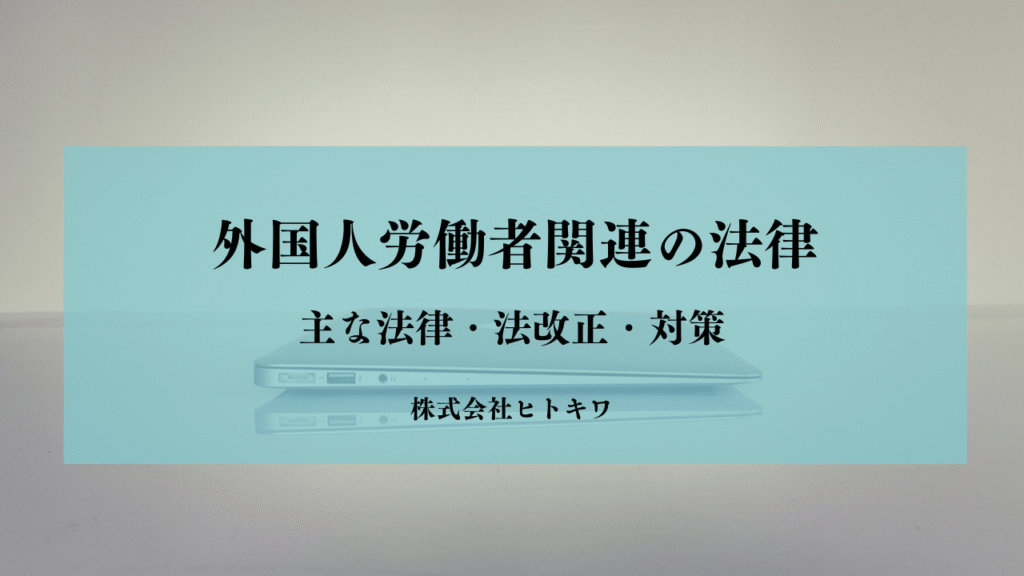
労働力不足が深刻化する日本において、外国人労働者の雇用は企業の成長を支える重要なカギとなっています。
しかし、外国人材の採用には、在留資格や労働条件に関する日本の法律を正しく理解し、適用することが必要です。
この記事では、外国人労働者と円滑な労働関係を築くため、労働基準法や入管法といった主要な法律の基本から、賃金や労働時間、就労の注意点まで、企業が知るべき情報を網羅的に解説します。
日本人労働者と同じく安心して働ける環境を整えるための具体的な方法もご紹介します。
外国人労働者雇用に関連する主な法律
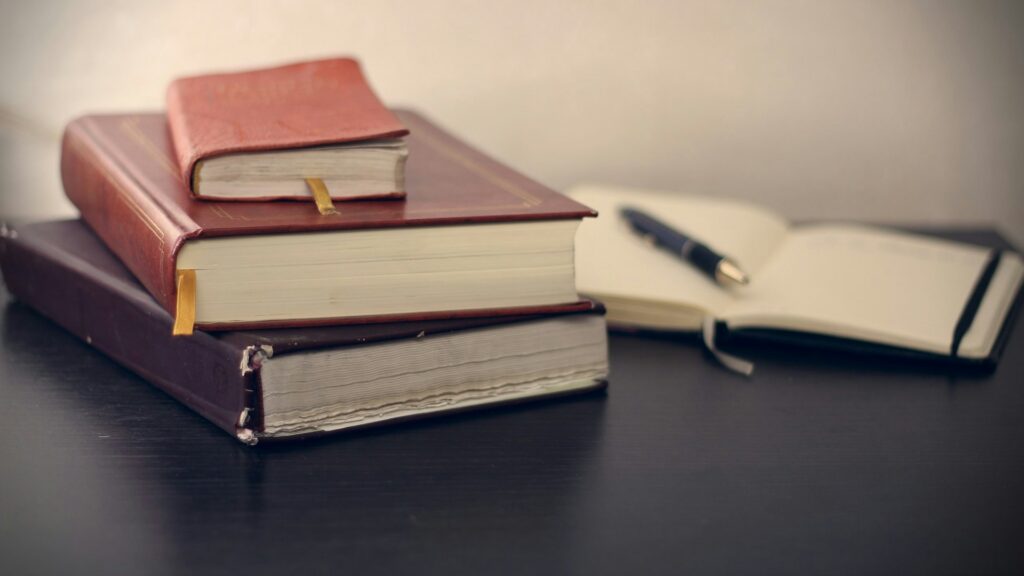
外国人労働者を雇用する際、日本の労働者と同様にさまざまな法律が適用されます。これらの法律を正しく理解し遵守することは、企業がトラブルなく外国人材を受け入れるための第一歩です。
ここでは、特に重要となる代表的な法律とその内容を解説します。
労働基準法
外国人労働者であっても日本人と同じように労働基準法が適用されます。
労働時間や賃金、休憩、休日、そして解雇に関するルールは、国籍に関係なくすべての労働者に守られなければなりません。
これは、不当な労働条件や差別を防ぎ、健全な労働環境を確保するために必要なことです。
外国人だからといって、日本人とは異なる労働条件を設定することはできませんので、注意が必要です。
(出典:厚生労働省「労働基準法」)
出入国管理及び難民認定法(入管法)
この法律は、外国人の日本での在留や就労を管理する上でもっとも重要なものです。
企業は、外国人を雇用する前に、かならず「在留カード」を確認し、就労が許可されている在留資格であるか、また、その在留資格で許可された業務内容であるかを把握する必要があります。
不法就労者を雇用すると、雇用主も罰則の対象となりますので、適切な在留資格の確認は、適正な採用活動を行う上で非常に重要です。
(出典:法務省「出入国管理関係法令等」)
最低賃金法
最低賃金は、国籍を問わずすべての労働者に適用されます。
外国人労働者に対しても、日本の最低賃金以上の賃金を支払う義務があり、これに違反すると法律違反となります。
特定技能や技能実習といった制度を利用する際にも、最低賃金はかならず守らなければなりません。
(出典:厚生労働省「最低賃金法」)
労働安全衛生法
労働者の安全と健康を守るための法律です。
外国人労働者も例外ではなく、安全な労働環境を提供し、災害を防止するための措置を講じる必要があります。
安全教育や健康診断の実施、危険な作業における保護具の提供などは、国籍に関係なく行うべき雇用主の義務です。
(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」)
労働者災害補償保険法
業務中の怪我や病気、あるいは通勤中の事故などに対して、補償を行う法律です。
外国人労働者もこの保険の適用対象となり、万が一の労働災害に備えるため、すべての労働者を労働者災害補償保険に加入させる必要があります。
これは、労働者を守るだけでなく、企業にとってもリスク管理の観点から重要です。
(出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」)
雇用保険法
外国人労働者が失業した場合に必要な給付を行うための法律です。
日本人と同様に、外国人労働者も一定の就労期間や労働時間を満たしていれば雇用保険の加入対象となります。
雇用保険に加入することで、労働者は失業手当を受け取る資格を得られ、企業は雇用の安定化に貢献できます。
(出典:e-Gov法令検索「雇用保険法」)
労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)
企業が外国人労働者を雇用する、または離職した際には、その状況をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
この法律は、国が外国人労働者の雇用状況を把握し、安定した雇用環境を整備するために重要な役割を果たしています。
この届出は、企業が適正に外国人材を採用し管理していることの証明にもなります。
(出典:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)
労働契約法
労働契約は、使用者と労働者の間で交わされる重要な合意です。
労働契約法は、その契約内容が公正であることや、労働者の権利が守られるように雇用主の義務を定めています。
外国人労働者との契約においても、労働条件の明示や契約内容の変更、解雇に関するルールなど、この法律に則って適切に行う必要があります。
(出典:厚生労働省「労働契約法」)
厚生年金保険法
外国人労働者も、日本人と同様に厚生年金保険の加入対象となることが一般的です。
これは、将来の年金受給資格や医療保険、失業保険など、社会保障制度の重要な部分を形成するものです。
外国人の雇用主は、労働者を厚生年金に加入させる義務があり、これにより外国人が日本で安心して労働できる基盤が整います。
(出典:厚生労働省「厚生年金保険法」)
外国人労働者を雇用する上でのよくある法律問題と対策

外国人労働者の雇用においては、文化や言語の違いから、予期せぬトラブルが発生することもあります。
特に、労働時間や賃金、解雇に関する問題は、法律違反に繋がりやすい重要な点です。
ここでは、外国人労働者の雇用でよくある法律問題とその対策を具体的に解説し、トラブルを未然に防ぐためのヒントを提供します。
①労働基準法違反を防ぐための労働時間と賃金管理
外国人労働者を雇用する際に最も注意すべきことの一つが、労働基準法の遵守です。
特に労働時間の管理は、日本人と同様に厳格に行う必要があります。
残業代や深夜手当の計算方法について、外国人労働者が十分に理解しているとは限りません。
そのため、雇用主は契約書や就業規則に労働条件を明確に記載し、労働時間の記録を正確に行うことが必要です。
②適切な契約書作成の重要性
外国人労働者と雇用契約を結ぶ際には、労働条件を明確に記載した契約書を作成することが必要です。
言語の壁があるため、母国語または外国人が理解できる言語で契約書を作成するか、翻訳を添付することが推奨されます。
賃金、労働時間、休日、業務内容、在留資格の有効期限などを細かく記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
③法律を守った採用活動の重要性
外国人労働者の採用においては、法律を守った活動が必要です。
特に、労働者の在留資格や就労資格の確認は徹底して行うべきです。
もし、不法就労者と知らずに雇用してしまった場合でも、雇用主は罰則の対象となる可能性があります。また、労働条件が明確でないと、後のトラブルの原因となります。
④外国人労働者が安心して働ける環境を整備する
外国人労働者が日本で安心して労働するためには、労働条件だけでなく、生活面でのサポートも重要です。
外国人が日本の法律や文化を理解できるよう、研修やオリエンテーションを実施することも効果的です。また、相談窓口を設けたり、多言語対応のサポート体制を整えることも必要です。
外国人労働者関連の法律改正について
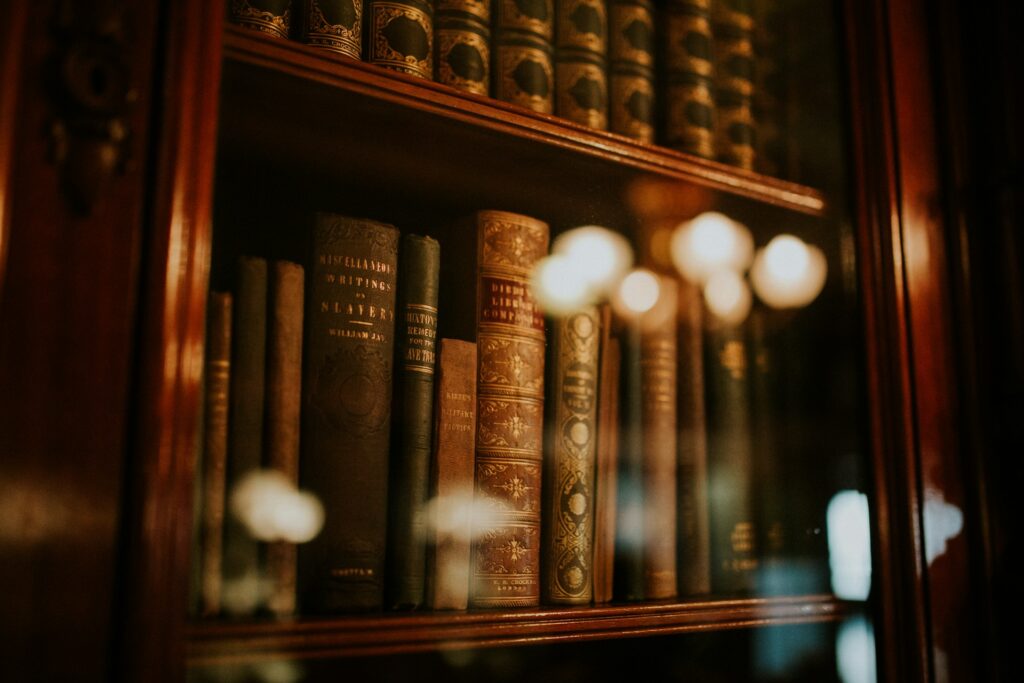
近年、外国人労働者の受け入れをめぐって、複数の法律改正が進められています。特に注目すべきは、従来の「技能実習制度」を廃止し、新たに「育成就労制度」を創設する動きです。
技能実習制度から育成就労制度へ
技能実習制度は、国際貢献という名目のもと、長年にわたり労働者の転職が厳しく制限されていましたが、技能実習制度により、過酷な労働環境や人権侵害といった問題が指摘され、多くの批判にさらされてきました。
一方で、新しく創設された「育成就労制度」は、労働者のキャリア形成を第一に考え、同じ分野であれば一定の条件下で転職を可能にする制度です。
育成就労制度が導入されることで、労働者自身がより良い労働条件を求めて動くことができるようになり、企業間の競争を通じて労働環境の改善が期待されています。
外国人労働者が自らの意志で就労先を選べるようになることは、彼らの人権保護を強化し、同時に企業にとっても優秀な人材の獲得につながります。
(出典:法務省「育成就労制度創設等に係る検討状況について」)
在留資格「特定技能」の拡充
現在の日本は、建設業や農業だけでなく、製造業、宿泊業、外食産業など多くの分野で深刻な人手不足に直面しています。
こうした状況に対応するため、特定技能の対象分野が大幅に拡大されましたが、これにより、即戦力となる専門的なスキルを持つ外国人材が、より幅広い産業で活躍できる道が開かれています。
特定技能には、一定の技能と日本語能力を要する「特定技能1号」と、熟練した技能を持つ「特定技能2号」があり、長期的な就労とキャリア形成が可能となるため、企業は安定した人材を確保できます。
この制度は、日本の労働市場の課題を解決する重要な鍵となっています。
改正入管法
2024年の法律改正は、日本の労働市場における外国人労働者のあり方を大きく変える動きとして注目されています。
外国人労働者が一定の要件を満たせば、雇用主を移籍できるようになる見通しです。
この改正の背景には、従来の技能実習制度で問題視されていた、労働者の人権保護や劣悪な労働環境の改善という強い目的があります。
雇用主の変更が可能になることで、労働者は不当な労働条件から逃れることができ、同時に企業は外国人労働者の定着率を高めるために、より魅力的な労働環境を整える努力が求められることになります。
これにより、日本全体の労働環境の底上げが期待されています。
(出典:法務省「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について」)
外国人労働者の法律に関するよくある質問
外国人労働者の法律に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。
Q1. 外国人を雇用する際に在留カードの確認はなぜ必要ですか?
在留カードには、外国人の在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されています。このカードを確認することで、外国人が日本で労働できる法律上の資格があるかを把握できます。もし就労資格のない外国人を採用した場合、雇用主は不法就労助長罪に問われる可能性があるため、採用前の確認は絶対に欠かせません。
Q2. 雇用した外国人労働者が辞めた場合、雇用主がすべきことはありますか?
外国人労働者が離職または死亡した場合は、外国人雇用状況届出として、離職後10日以内にハローワークへ届け出を行う必要があります。また、離職後も在留資格を維持できる外国人がいるため、労働者が円滑に次の就労先を探せるよう、情報提供などの支援をすることも大切です。
Q3. 外国人労働者の賃金は、日本人より安く設定してもいいですか?
外国人労働者の賃金は、日本人と国籍を理由として差別してはならないと法律で定められています。同じ業務内容や労働時間であれば、日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。もし最低賃金以下の賃金を支払った場合、最低賃金法違反となり、罰則の対象となります。
Q4. 外国人労働者を解雇する際の注意点は?
外国人労働者を解雇する際も、日本人と同様に労働基準法が適用されます。不当な解雇は法律違反となるため、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる必要があります。解雇予告期間の遵守や、解雇理由を明確に伝えることが必要です。
Q5. 外国人労働者の採用時に、日本語能力はどの程度必要ですか?
日本語能力の必要度は、労働内容によって異なります。就労する外国人の在留資格によっては、日本語能力試験の合格が必要な場合もあります。コミュニケーションが円滑に行えるよう、日本語能力のレベルを採用前に確認することが必要です。
まとめ:外国人労働者と企業のより良い関係を築くために
外国人労働者の雇用は、企業に新たな価値をもたらす素晴らしい機会です。
法律や制度を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、トラブルなく、外国人労働者と企業が共に成長できる関係を築くことができます。
この記事が、外国人労働者の雇用を検討している皆さんの参考になれば幸いです。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。
電話やLINEでお問い合わせ可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。