【わかりやすく簡単に!】技能実習生とは?特定技能の違いや制度の目的
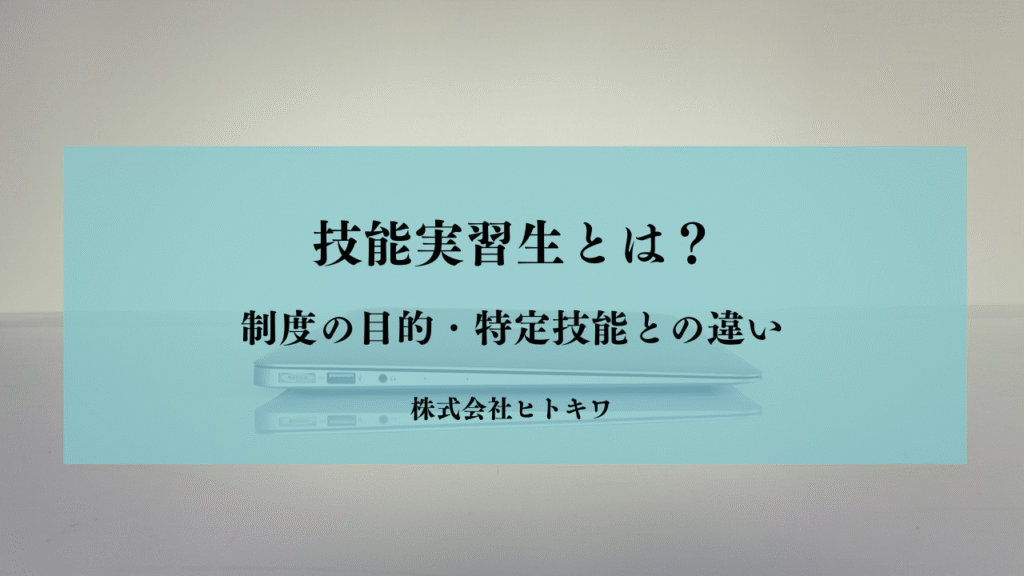
技能実習生制度は、日本の企業が開発途上国の若者へ技能や技術を伝えることで、その国の経済発展を支援する国際協力の制度として実施されています。
その目的は人材育成を通じた国際貢献という理念に基づきますが、実際には人手不足を補う手段として利用されている側面が強く、理念と実態の乖離が大きな課題として指摘されています。
最近では特定技能との違いや、実習生の労働環境に関する技能実習生問題など、さまざまな課題も指摘されるようになりました。
この記事では技能実習生の基本的なしくみや特定技能との明確な違い、さらに問題点と今後の制度の見直しについてわかりやすく解説していきます。
技能実習生制度とは?目的としくみ

技能実習生制度は日本が国際貢献のために作った、外国人材の技能育成を目的とした制度です。
ここでは、まず技能実習生が日本の企業で働くことの概要をお伝えし、その目的と実習の実施に必要な監理団体を含めた基本的な仕組みをわかりやすく解説していきます。
① 技能実習生とはどのような制度か?
技能実習生制度とは、開発途上国の若者などを技能実習生として日本の企業に受け入れ、技術や知識を習得してもらう制度のことを指します。
国際協力と人材育成を目的としており、技能実習生は日本の企業との雇用契約に基づいて実施者のもとで働き、実習を行います。
在留資格としては「技能実習」が付与され、職種ごとに定められたカリキュラムに沿って技能を身につけることになります。
この制度は、母国での活躍を目的としているため、原則として実習期間を終えた技能実習生は帰国することが前提となっています。
実習期間は、技能実習の計画や段階に応じて最長で5年間と定められています。
② 制度の簡単な目的と基本的なしくみ
技能実習生制度の最大の目的は、日本の優れた技術や知識を開発途上国へ移転し、その国の経済発展をサポートすることにあります。
技能実習生は日本に来てから1号(入国後約1年間)、2号(約2年間)、3号(約2年間)という三つの段階を経て実習を行います。
受け入れる企業は、技能実習を適正に実施するために、監理団体という非営利団体のサポートをかならず受ける必要があります。
監理団体は、技能実習の計画が適切かどうかをチェックしたり、実習生の生活指導や企業への監査を行う機関です。
この二つの機関が連携し、技能実習生が安心して技能を学べる環境を整えることが制度の基本的なしくみとなっています。
外国人技能実習生を受け入れるメリット・デメリット

技能実習生の受け入れは、企業にとって大きなメリットがある一方で、さまざまな必要な手続きや費用、文化の違いなどデメリットも存在します。
このセクションでは、まず技能実習生を受け入れることで企業が得られるメリットを詳しく確認し、次に受け入れる際に知っておきたいデメリットについてもわかりやすく見ていきます。
③ 外国人技能実習生を受け入れるメリット
技能実習生を受け入れることにより、人手不足が深刻な職種において企業は安定的な人材の確保ができるという大きなメリットがあります。
外国人の実習生は学ぶ意欲が高く、熱心に作業に取り組んでくれるため、企業内の活性化にもつながることが多いです。
また、国際貢献という目的を持った制度であるため、企業のCSR活動の一環として社会的な評価を高める効果も期待できます。
さらに、技能実習生が母国に帰国した後も、日本で身につけた技術や知識を活かして活躍することで、企業と母国との関係を深めることにもつながります。
実習生が日本での実習を頑張ってくれることは、企業の長期的な成長にもつながることなのです。
④ 外国人技能実習生を受け入れるデメリット
技能実習生を受け入れる企業には、実習生の生活指導や日本語教育、監理団体との連携など、さまざまな必要な作業や実施事項が発生します。
外国人である実習生との文化や習慣のちがいから、意思疎通の難しさや生活環境の整備に手間がかかることもデメリットの一つです。
また、技能実習生の給与は日本人従業員と同等以上である必要があることや、監理団体への費用、渡航費用など受け入れにかかるコストも無視できません。
実習生が途中で辞退したり、帰国してしまったりするリスクもゼロではないため、技能実習の計画どおりに実施できない可能性も考慮しておく必要があります。
技能実習生と特定技能の違い
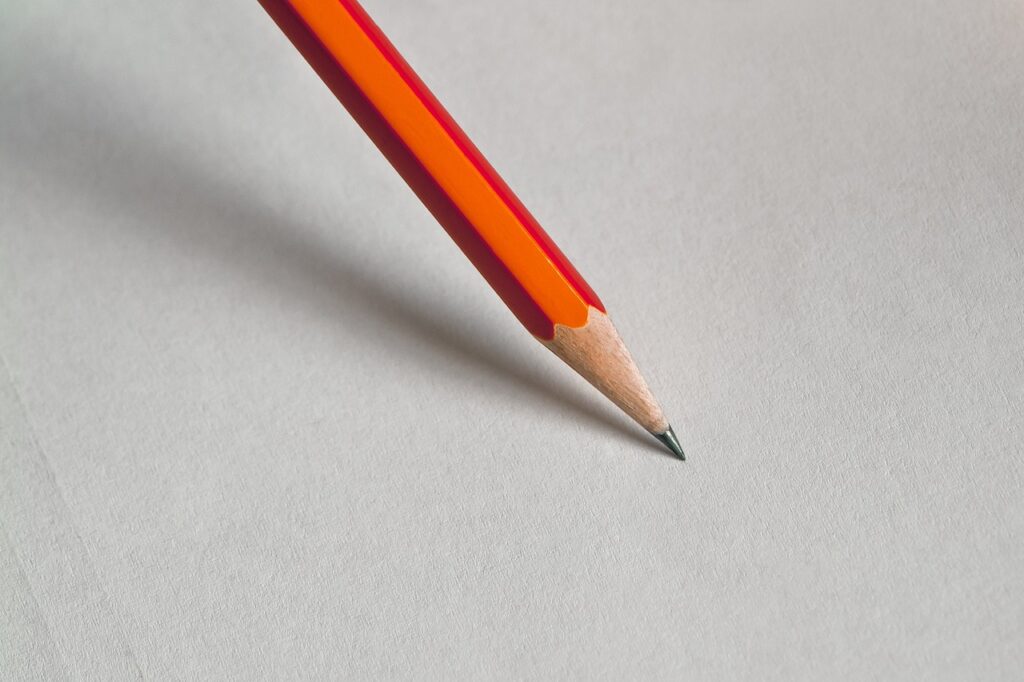
技能実習生の制度を理解する上で、外国人の就労を目的とする「特定技能」との違いを知っておくことは欠かせません。
このセクションでは、まず特定技能制度が導入された背景や、それぞれの制度の目的と在留期間の違いを比較します。
さらに、介護など特定の職種における実習生制度の特徴についてもわかりやすく解説していきます。
⑤ 特定技能制度の違いと導入背景
特定技能制度は、日本国内で人手不足が特に深刻な産業分野において、外国人の就労を目的として創設された新しい在留資格です。
これに対して技能実習生制度は、国際貢献を目的としていることが根本的な違いであり、技能の習得が中心です。
特定技能の外国人は、即戦力として働くことが期待されており、技能実習生のように監理団体による厳しい監理の必要がないことも特徴です。
しかし、特定技能の実施には特定技能登録支援機関によるサポートを受けることが推奨されています。
⑥ 特定技能との違いを目的・在留期間で比較
技能実習生制度と特定技能制度の違いを明確に見ていくことは大切です。
技能実習はあくまでも技能を身につけて母国に帰国することが目的であるため、在留期間は最長5年間と定められています。
一方で特定技能は就労が目的であり、在留資格は1号と2号に分かれており、特定技能2号を取得すれば更新を繰り返して半永久的に日本に在留できることが大きな違いです。
技能実習を修了した技能実習生は、所定の試験に合格すれば特定技能1号への在留資格を変更できることも覚えておくとよいでしょう。
このように、目的と在留期間に明確な違いがあることを企業は理解しておく必要があります。
(出典:法務省「特定技能制度」)
⑦ 介護分野における実習生制度の特徴
介護分野は、日本国内で外国人材の必要性が特に高い職種の一つであり、技能実習生制度と特定技能制度の両方で受け入れが可能です。
介護の職種で技能実習を行う実習生は、日本の介護現場で専門的な知識と技術を学びます。
技能実習2号を良好に修了した実習生は、特定技能1号への移行時に試験が免除されることが特例として認められています。
ただし、介護分野は特定技能2号の対象外であるため、長期的な日本への在留を目的とする場合は、別途「在留資格:介護」への移行を検討する必要があることを理解しておきましょう。
技能実習生問題の背景と改善に向けた動き

国際貢献を目的とした技能実習制度ですが、実施の過程で実習生の賃金や人権に関する問題がさまざまに指摘され、技能実習生問題として社会的な関心が高まっています。
ここでは、具体的な賃金や人権に関する問題、実習生が企業を離脱したり帰らないといった失踪の背景をわかりやすく解説し、それを受けて進められている制度の見直しについてもお伝えしていきます。
⑧ 賃金や人権に関する問題
技能実習生の労働条件が不当であったり、日本人と同じ作業をしているにもかかわらず賃金が低かったりすることが、問題として指摘されています。
賃金は日本人の最低賃金以上でなければならないという制度上のルールがあるにもかかわらず、実際にはそこが守られていないケースが報告されているのです。
また、移動の自由が制限されたり、パスポートを受け入れ側の企業が取り上げてしまったりするような人権侵害にあたる行為も残念ながら存在しています。
これらの問題は、技能実習生制度が本来持つ国際貢献の目的を大きく損なうことであり、技能実習生の就労環境を整備することが急務です。
⑨ 実習生が帰らないケースと失踪の背景
技能実習生が実習期間を終えずに途中で企業から失踪してしまったり、期間が過ぎても母国に帰らないというケースも問題になっています。
失踪の背景には、不当に低い賃金や長時間労働、ハラスメントなど、劣悪な労働条件から逃れたいという実習生の切実な思いがあることが多いです。
技能実習の目的と実施の実態が異なっていることや、監理団体の監理が十分に機能していないことも、実習生を追い詰めてしまう原因の一つとなっています。
実習生が安心して日本で技能を学べる環境を整え、実習を途中で諦めさせないことが、この問題を解決するための鍵となります。
⑩ 制度の見直しと今後の展望
技能実習生問題への対応として、日本政府は技能実習制度の廃止を決定し、「育成就労制度」へ移行する方針を打ち出しています。
新しい制度は、人材育成を通じた国際貢献という理念を維持しつつ、実習生の就労や人権保護をより一層強化することが目的です。
特に、実習生の転籍・転職種を一定の条件で可能にするなど、人権に配慮した柔軟な対応が取り入れられることが議論されており、実施者の役割も大きく変化していくことが予想されます。
技能実習生が、より良い環境で日本の技術を学び、母国へ持ち帰って活躍できるよう、制度の改善に期待が集まっています。
特定実習生に関するよくある質問(FAQ)
技能実習生制度や特定技能制度について、受け入れを検討している企業様や、制度に関心がある方からよくいただく質問をまとめてみました。
技能実習生の在留期間や特定技能への移行、費用に関することなど、気になることがあればぜひこちらで疑問を解消してくださいね。
⑪ 技能実習生は最長何年日本で働けますか
技能実習生として日本に在留できる期間は、技能実習の段階に応じて定められており、最長で5年間となっています。
入国後、1号(約1年間)、2号(約2年間)、3号(約2年間)という三つの段階で実習を行い、期間満了後は原則として帰国が前提です。
ただし、特定技能1号へ在留資格を変更することで、引き続き日本で働くことができる道もあります。
⑫ 特定技能に移行するための条件は何ですか
技能実習生が特定技能1号へ移行するには、まず技能実習2号を技能検定3級合格や出勤状況などを含めて「良好に修了」していることが必要となります。
移行先の職種が実習と同一分野であれば試験は免除されますが、異なる分野へ移行する場合は技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。
特定技能への移行は、実習生にとって日本でさらに長く働くための重要な道筋となります。
⑬ 実習生は途中で仕事を変えることはできますか
技能実習生は、決められた実習計画に沿って技能を実施することが前提のため、原則として受け入れ企業や職種を途中で変更することはできません。
例外として、企業側の都合で実習継続が困難になった場合や、実習生に対する人権侵害などが発生した場合には、転籍や転職種が認められることもあります。
特定技能の在留資格へ移行すれば、同一職種内での転職は認められますので、制度による違いを理解しておきましょう。
⑭ 技能実習生を受け入れる側の費用はいくらですか
技能実習生の受け入れにかかる費用は一律ではありませんが、主な費用は渡航費用、監理団体への会費や費用、実習生の入国後研修費用などです。
また、実習生へ支払う賃金は日本人労働者と同等以上であることがかならず定められており、費用の中で大きな部分を占めます。
このほかにも、住居の確保にかかる費用なども企業が負担することが多いです。
⑮ 実習生を雇用する上でかならず守るべきことは
技能実習生を受け入れる企業は、実習生の安全と人権をかならず守り、日本の労働関係法規を順守する必要があります。
最低賃金の順守や長時間労働の防止など、日本人労働者と同等の待遇を確保しなければなりません。
また、技能実習の目的である技能習得が計画どおり実施されていることを監理団体と確認し、母国の文化に配慮した生活指導を行うことも重要です。
まとめ
技能実習生制度は、開発途上国への国際貢献を大きな目的としており、日本の技術や知識を伝えることを目的とした大変意義深い制度です。技能実習生は、日本の企業で働きながら実習を行い、技能を習得することになります。しかし、近年では労働環境や人権侵害といった技能実習生問題も指摘されており、制度の抜本的な見直しが進められています。特に特定技能制度との違いを理解することは重要で、技能実習が技能の習得目的であるのに対し、特定技能は就労が目的という違いがあります。今後制度が改善されていく中で、外国人実習生が安心して日本で活躍できるよう、受け入れ企業はかならず制度の目的とルールを理解し、適切な実施と監理を行うことが必要となります。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。